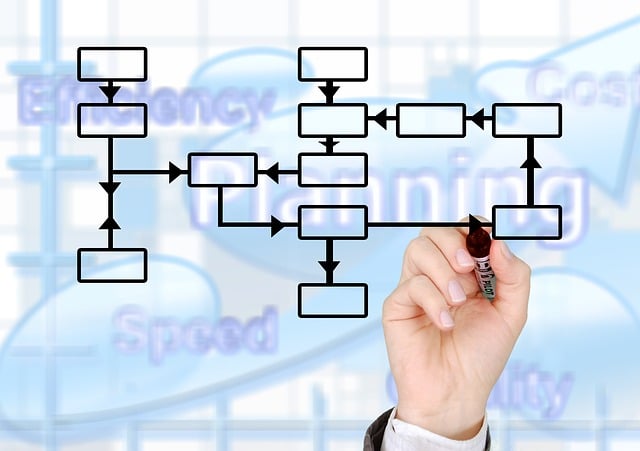□ 第十章 青写真 □
正月三が日はあっという間に過ぎた。四日から会社に出向き仕事した。会社は九日までは休業である。この間は通常会社には入れないが、早川は四日からの仕事をする旨を、予め会社に届けて許可を得ていた。
悟は横浜への帰り際に、手紙待ってるからなとアキに言って篠ノ井を後にした。だが、待てど暮らせどアキからの手紙は来なかった。まさか賭けに負けたことを認めていないということじゃないだろうな。それとも単純に忘れているだけか? どういう告白文が届くのか、ワクワクして何度も社宅の集合郵便受けに足を運んだが、アキからの手紙は届いていなかった。電話して催促する気にもなったが、こういう場合そっとしておくに限ると思い直した。
一月七日の土曜の夜、悟は篠ノ井の家に行った。明後日の九日は、いよいよ弟の謙二がこの篠ノ井の家を訪れることになっている。
一月九日の篠ノ井は晴れ模様だったが、時折り雪がパラつき寒かった。悟の弟謙二は、東京駅で六時半ごろの新幹線に乗った。新幹線が長野駅に着いた時は八時を少し回っていた。信越線の連絡は八時二十二分発があったが、せっかく来た初めての地である、少しのんびりしようと思い、一本遅い八時四十三分発の電車に乗ろうと決めた。腹ごしらえをしようと思い駅近くの茶店に入った。そこから、兄の悟に九時前に篠ノ井駅に着く旨の電話を入れた。兄から東口に降りるように指示された。
悟はアキに謙二の到着時刻を告げた。頃合いをみて、リコも含めた三人で車に乗り込み駅に向かった。リコはいくぶん緊張気味である。
「リコは弟の顔はもう覚えたか?」
「はい。しっかり頭に入っています」
リコは運転しながら答えた。
「写真と実物は少し違うからなあ」
「えっ、お兄さん、それってどういうこと?」
「あはは、びっくりすることないじゃないか、良く言うだろ? 写真写りがいいとか悪いとかその類だよ」
「弟さんはどっちなの?」
「気になるか?」
「いえ、気になるってほどでもないですけど、ただ聞いてみたかっただけです」
アキは二人の会話を聞いていて、リコが悟の弟に対してより一層興味を持ってると感じた。
「あはは、あと十分もすれば弟に会えるから、その時じっくり見たらいいよ」
「……あと十分、ヤダ、緊張してきたわ」
リコが独り言を呟いた。
「それはないだろう? 緊張しないために写真を見てたんだろ?」
「そうですけど、やっぱり、いざとなるとヤバいなあ。運転がどうかなりそう」
「おいおい、大丈夫かよ代わろうか?」
「いえ、もう大丈夫です。落ち着きました」
アキはそう簡単に落ち着く筈がないと思った。さあ、今日のリコ劇場がどうなるのか楽しみになってきた。
駐車場に少し早目に到着したが、三人は東口の改札口で謙二を待った。九時頃のこの時間帯は、乗降する客はさほど多くなかった。
暫らくして改札口の向こうから、手を上げて近づいて来るスーツ姿の男がいた。片手に紙袋を下げていた。謙二が改札口を出て三人に近づいてきた。謙二は終始嬉しそうであった。悟の傍に立っている二人の女性に会釈して、兄弟は握手した後、久しぶりの再会の喜びを抱き合って表現した。
アキは、日本で、ましてやこの田舎の町で、兄弟が抱き合って再会を喜ぶイメージを持ち合わせていなかった。だから、奇異に映ると同時に、何か新鮮なものを感じた。
「兄貴、久しぶりだな元気そうで何よりだ」
「お前も元気そうだな。今日は遠路はるばる悪かったな」
「なーに、兄貴に会えると思うと、何処でも飛んで行くよさ。それに、やっぱり、こういう所はいいねえー、空気が美味しいし心が洗われる感じだね」
謙二は辺りを見回しながら言った。濃紺のスーツと朱色の縞柄のネクタイに身を包んだ、爽やかな印象の青年の姿だった。アキもリコも、謙二の顔を実際に見るのは初めてである。目の前の謙二を見て、アキは悟の身内ということもあるが、兄の悟を彷彿させる顔立ちに、訳もなく親しみを覚えた。写真よりも、はるかに好青年と言うかカッコ良かった。
リコは写真のイメージとは似てはいるものの、実際の笑い顔や目の動き、手のしぐさなどの立ち居振る舞いをみて、写真とは明らかに違うと思った。車の中で悟が、写真と実物は少し違うからなあと言った意味を理解した。写真なんて、所詮は2Dの世界で3Dには及びもつかないと思った。悟が言っていた実直で真面目な顔が目の前にある。しかも、相当なイケメンである。胸がドキドキしてきた。
「おっと、ごめん。紹介するよ。こちらが姉さんで、名前が亜希子さん。こちらが私の弟の謙二です」
悟は亜希子と謙二を引き合わせた。
「オォー、嬉しいなあ、この方が噂の?」
謙二は亜希子を見て、悟の方にチラッと視線を送った。
「そういうこと」
「あ、失礼しました、弟の早川謙二と申します。宜しくお願い致します」
謙二は亜希子の顔を見て丁重に頭を下げた。
「花岡亜希子と申します。こちらこそよろしくお願い致します。……どんな噂だったのかしら?」
亜希子も腰を折って頭を下げた。そして謙二の顔を見て微笑んだ。
「いえね? 兄貴が言うには、とにかく世界で一番の女性に出会えたんだよと、それはもう、呆れ返るほど自慢するんですよ」
「あら、そうでしたの?、悟さん、ありがとう」
亜希子は嬉しかった。
「今、お会いして納得しました。兄貴の女性を見る目も満更じゃないですね」
「この野郎、初めて会った人に失礼だろう? そんないい方」
「あは、ごめん。だって、思った通りを言ったまでだよ。これでも誉めたつもりだけどなあ」
謙二は頭に手をやり無邪気に笑った。率直そのものである。
「そうか、それは、それは、ありがとう。……えっ、何かはぐらかされた感じだな。……そんなことより、ほら、ご挨拶の握手、握手」
悟に促されて亜希子は慌てて手袋をはずした。そして、お互いに宜しくと言いながら握手した。謙二は少し照れていた。
「こちらが、妹さんの真理子さん」
悟は、亜希子の横に恥ずかしそうに立っている真理子に謙二を紹介した。
「早川謙二といいます。宜しくお願い致します」
謙二は頭を下げた。そして真理子の顔を見た。妹がいるなんて、悟からは一度も聞かされていなかった。それだけに心の準備が出来ていなかった。
「花岡真理子と申します。宜しくお願い致します」
真理子も深く頭を下げた後、謙二の顔を見た。真理子の顔が少し赤らんだ。明らかに緊張している顔である。
「ほら、謙二、美人を前にして何を突っ立ってんだよ、ご挨拶の握手、握手」
真理子は予め手袋を外していた。謙二も真理子も、お互いに目を合わせ慌てて握手した。謙二は真理子の柔らかで温かい手に触れ、今まで感じたことのない、何か不思議な感情が走った。真理子は、さっきから胸がドキドキはしていたが、謙二の手に触れた瞬間、理由もなく心臓が激しくドッキンドッキンと暴れ始めた。心臓の音が、謙二に聞こえるのではと心配するくらいであった。
アキは真理子と謙二の様子を見て、これは、もしかしたら、もしかするかもと思った。
「じゃあ、寒い所にいつまでも立っていたってしょうがないから行こうか?」
謙二は後部座席から、助手席の亜希子に紙袋を手渡した。
「これ、神戸のお土産です」
「あら、すみません。そんなに気を使わなくてもよろしいですのに、……じゃあ、遠慮なくいただきます。ありがとうございます」
「男ってこういう場合まるで駄目ですね。何にしたら良いのか選ぶのに迷ってしまって、……ですから、お気に召すかどうかは保証の限りではありません。ま、気持ちと思ってください」
アキは謙二の語り口に好感を持った。心の内がそのまま言葉になっていて実にストレートである。運転しながら聞いていたリコも同じ思いだった。胸のドキドキが次第にルンルン気分になっていった。
家に着き、悟と謙二はリビングのソファに並んで腰を下ろした。初めてのお客さんは、八帖の客間に通すことになっていたが、悟の弟ということでリビングに通された。リコがリビングを出て、両親に謙二の訪問を告げに走り、又すぐ戻って来た。
「東京を早くに出発されたでしょうから、お食事はまだでしょ? お作りしましょうか?」
「いえ、長野駅で済ませてきました。心遣いありがとうございます」
「そうでしたか、じゃあ、コーヒーでもいかがですか?」
アキが謙二に聞いた。朝食の時コーヒーは飲んだが、兄と同じで、コーヒー好きの謙二は嬉しそうな顔をした。
「あ、すみません。いただきます」
「悟さんもコーヒーでいい?」
「だな」
アキは台所に向かった。リビングの壁には、クリスマスイブや餅つきや初詣のほかに、カラオケなどの写真が所狭しと張られていた。こうして見ると、短い間に随分と多くのイベントを楽しんできたんだと悟は思った。
アキがコーヒーを運んできた。
「どうぞ。お口に合いますかどうか、……もうすぐ両親が来ると思いますが、少しお待ちください」
「アキもリコも座ったら?」
悟がアキの顔を見ながら言った。
「あら、私たちは遠慮したほうがいいんじゃない? お仕事の話でしょう?」
「そうだけど、……だな、一応お父さんに聞いたほうがいいかな」
アキとリコは台所に消えた。
「田舎はどうだった?」
「母さんも姉さんも元気だった」
「で、話してくれたんだろ?」
「話した。母さんも姉さんもすごく喜んでいたよ。母さんなんか気が早いなあ、早く孫の顔を見たいなって言ってた」
「そっか、ありがとな。……同窓会か何かあったんだろ? 出席したのか?」
「出席した。楽しかったよ」
「女の子も来たんだろ?」
「そうだな、むしろ女の方が多かったな。男は大抵、東京とか大阪辺りに働きに出るからな。帰ると言っても金がかかるし大変だよ」
「だよなあ、……で、同級生の中で、気に入った女性はいないのか」
「残念ながらいないなあ。それに同級生ってさ、そんな目で見ないから、……つまり、恋愛対象として見れないよなあ、どうしても」
「そうか、それもあるかもしれないが、結局はお眼鏡にかなった奴がいないってことだろ?」
「そうな、今のところは」
「お前のことだから、女の子から言い寄られたりすることが結構多いんだろう?」
「そんなことを感ずる人も結構いるけど、ピンと来ないって言うか、気が進まないんだよなあ」
「同級生じゃなくても、姉さん達から、いい子がいるなんて情報は聞かないのか?」
「うーん。例えあっても、彼氏がいたりすると思うんだよな、たまに帰って、時間もないし煩わしいよな」
「そうかあ、いろいろ難しんだなあ」
「あの写真は?」
謙二が壁に貼ってある写真を指差した。
「年末年始の写真さ。結構多いだろ?」
「だなあ、後でじっくり見ていいかなあ」
「もちろんいいだろうけど、どうだろうか、そんな時間があるかなあ?」
その時ドアが開いて両親が姿を現した。悟と謙二は瞬間的に腰を上げ軽く会釈した。
「ご紹介します。弟の謙二です」
悟は、弟を義父の誠一郎に紹介した。
「オォーー、謙二君か、よく来てくれたね」
誠一郎の顔は笑っていた。謙二の顔をジッと見ていた。謙二は少し緊張気味であったが、スーツの内ポケットから名刺入れを取り出した。
「早川謙二と申します。兄が大変お世話になっております。今日はご挨拶に参上致しました。よろしくお願い致します」
謙二は誠一郎に名刺を渡しながら口上を述べた。誠一郎は謙二に名刺を渡しながら、また武士が一人増えたと思った。
「遠路はるばるご苦労だったね。ま、ゆっくりくつろいでくれ」
誠一郎は、二人にソファに腰を下ろすように手で促し、母の典子と共に自らもソファに腰を下ろした。
「あ、お父さん、すみません、亜希子と真理子も同席したほうがいいですか?」
悟はさっきから気になっていることを聞いた。
「そうだな、仕事の話が中心になるが、参考になることもあると思うから、その方がいいかな。母さん呼んできなさい」
母典子は、はいと言って席を立った。暫らくして、台所にいた亜希子と真理子が、コーヒーを盆に乗せて現れた。そして、ファに腰掛けた。誠一郎は謙二の名刺をジーッと見て顔を上げた。
「謙二君は今日の夕方には、悟と一緒に東京に戻ると悟から聞いているが、その予定かな?」
誠一郎は確認した。謙二は誠一郎が兄のことを、悟と呼び捨てにしていることに少なからず驚いた。と同時に、兄がこの家族にかなり深く溶け込んでいるのだなと理解した。
「はい。明日予定が入っておりますので、そのようにさせていただきたいと思っております」
「謙二君のことはかねがね悟から聞いていたが、悟が言っていた通りの青年だな」
「兄が私のことをどのように申したかは存じ上げませんが、未熟者には変わりございません。どうか、ご指導宜しくお願い致します」
アキは謙二のしっかりした口調の中に、相当な自信を持っているなと感じた。リコは、とてもしっかりした人だなと思いながら、ただただ見とれているばかりだった。
「今日はせっかく来てもらったついでで悪いのだが、謙二君に相談したいことがあるんだが、いいかなあ?」
謙二は挨拶だけだと思っていたし、悟から父親が是非会いたいと言っていたとは聞いていたが、相談があるとは聞いていなかった。
「えっ、私に相談、……で・す・か? ……私如き若輩者にですか?」
「悟に教わったことがあるんだよ。年齢と言う先入観で物事を判断しては、実態を誤って見てしまうとね」
「そのことでしたら、私も同感です。先入観と言うものは、心のバリアの中に巣食ってる最も悪い知識だと心得ております」
誠一郎は唖然とした。この若者から、何故このような言葉が飛び出してくるのだ。アキも大変な驚き様だった。弟からも心のバリアと言う言葉が発せられた。異次元の二人を見たような気がした。悟は、謙二の話しぶりを聞いて苦笑いした。来たぞ、来たぞー。
「だから、謙二君を一人の立派な実業家と思い、折り入って相談したいことがあるんだよ。いいだろ?」
誠一郎は優しいまなざしを謙二に向けた。
「そうですか。そこまでおっしゃるんでしたら、お役に立てるかどうか自信はありませんが、喜んで」
「そうか、ありがとう。……悟、悪いけど、今、謙二君の話しぶりを聞いて気が変わった。……時間がないから、これからすぐに、謙二君を会社に連れていき、一通り社内を見て貰いたいと思っているんだが、どうかなあ?」
「それがよろしいかと思います。私は同席せず、お父さんと謙二だけでじっくり、お話しされた方がいいと思っていました」
悟は、このような事態になることを、予め察していたようである。元旦の日の家族での話し合いの中で、同席しないほうがいいと思うと言ったにも拘らず、一緒になって話を聞いといてくれ、と頼まれた経緯がある。
「そうか、そういうことだったのか、分った。じゃあ、すまんが謙二君、俺について来てくれないか?」
謙二は悟の顔をチラッと見た。悟は頷いていた。
「はい。分りました。お供致します」
父誠一郎と謙二はリビングルームを出ていった。
リビングルームに残された四人は、コーヒーを飲みながら談笑した。母親の典子がニコニコしながら口を開いた。
「お若いのに、随分としっかりした弟さんね。感心したわ」
「ありがとうございます。弟は小さい時から、いろいろ苦労して育って来ていますから、自立心が人並み外れて強いように思います。ですから、どんな事にも微動だにしない、強い精神力を持ち合わせているように思います。兄の私が言うのもなんですが、強い意志でコツコツと努力している姿を見て、大した奴だと思っています」
悟は弟を自慢した。
「悟さんがいつも自慢しているだけの弟さんだわ。目がキラキラしていて実直そうで頼もしい人みたい。……ね、リコ?」
アキがリコの方を振り向いて言った。
「ええ、悟お兄さんからお借りした写真を見て、頭でイメージしていたんだけど、実物は全然違って見えました。想像以上に素敵で、とっても爽やかな感じがしました」
リコはもう完全に虜になってしまったのでは、と思わせるような発言をした。悟は弟の謙二が褒められたことに、とても嬉しそうな顔になった。それを見てアキは、兄弟の心の奥でつながっている強烈な絆を感じ、とても羨ましく思った。
「リコ、タイミングを見て、弟も含めた家族全員の写真を撮っといてくれないかなあ。謙二とはそう頻繁には会えないし、いい記念になると思うんだよな」
「あ、はいそうですね。分りました。ツーショットも撮っていいですか?」
「もちろんだよ、リコの好きなように撮ったらいいさ、……な、アキ」
「ええ、いいと思うわ。さりげなくそれとなく、自然な姿を思い切って撮ったらいいのよ。その代り、ピンボケだったら許さないからね。リコの腕の見せ所よ」
「分りました。手が震えてきそうね。でも嬉しい」
リコはとびっきりの嬉しい顔をした。
「それと、お昼ご飯のことだが、謙二と二人っきりで外で食べたいのだが、いいかなあ?」
「あら、どうして?」
「暫らく会ってなかったし積もり積もった話があるんだよ」
「それだったら、東京に帰る時、新幹線の中とかでも出来るんじゃありません?」
「……うん。分るけどな」
「できたら、せっかくいらしたのに一緒に食事したいわ。腕も振るいたいし、ね、リコどう思う?」
「私もお姉さんの意見に賛成」
「……うーん。……だけど」
「何か考えがあるのね? 何かが、たくっ付いて来たの?」
アキが悟の顔を見つめた。
「それほどでもないけど、物事にはタイミングがあるからなあ。……ま、いいか。じゃあ、一緒に食事させてもらうか」
悟は、考えていたことを諦めたような素振りをした。そう言われると気になるのがアキの性分である。多分、悟の考えは、父親と謙二の話の内容を聞き出しておこう、という算段だと思った。その上で、アキやリコ、場合によっては家族全員に話す内容が違ってきたり、十四時からの養成講座のこと考えた上でのことじゃないかと推察した。そうなると、新幹線に乗ってからでは遅いのである。悟が物事にはタイミングがあるからなあと言ったことと一致する。
「やっぱり、何か考えがあるみたいね。じゃあ、こうしたらどうかしら、一緒にみんなで食事して、それから二人で茶店でも行ったら?」
「おォーー、それはいい案だな、アキの作った料理も弟に食べさせたいしな。うん、気に入った。そうしよう」
「でも、余りゆっくりはできないかもしれませんね。お父さん次第だけど」
「だな、ま、いいよ、三十分もあればいいと思うから」
「そうなの? あたしとリコも同席しては駄目なのかしら?」
「俺もそれを考えたんだが、……うーん。じゃあこうしようか、早めに十一時半から食事して三十分で食事を終わらせる。そして、俺と謙二が近くの茶店に行く。三十分後つまり十二時半にリコと一緒に来たら? ちょっと慌ただしいけど、どうかな?」
「あら、さすがねいい案だわ。賛成」
「お父さんと謙二の話が、午前中で終わってくれるといいんだがなあ。そしたら、講座の始まる十四時まで茶店におれるからな」
「もしそれが駄目だったら、こういう案どうかしら。講座を早めに、例えば一時間ぐらいで終えて、帰る時駅に行く途中に茶店に寄るってのは? そしたら、謙二さんから講座の感想とかも聞けそうだし。……そうなると、茶店に二回も行くことになるけど、でもいい方法じゃないかしら」
「最近、アキにもビュンビュン何かがくっ付くようになったみたいだな。素晴らしい案だな」
「ふふ、悟さんの脳味噌を少しお裾分けして貰ったの、リコ、ごめんね」
アキはリコに笑顔を振りまいた。
「お姉さん、ずるい。いつの間に?」
「リコも最近は素晴らしい発言をするようになったじゃないか、自信を持てよ」
「お兄さんに言われると、すぐにその気になっちゃうのよね私。ふふ」
「まあ、リコったら呆れた言い草ね」
「じゃあ、アキの提案で行こうか。講座は今日が最後になるけど、もう取り敢えず教えることもなくなったし、一時間もあればいいだろう」
「そうと決まれば、食事の支度しなくっちゃ。リコとお母さんお願いね。暫らくしたら私も行くから」
「はい、はい。急ぎましょう」
ニコニコしながらじっと聞いていた母親が腰を上げ、リコを手招きしながら台所に消えた。
「お父さん達、どんな話しているのかしらね」
アキが悟の顔を伺いながら話した。
「そうだなあ、会社の内部を見せるってことに意味がありそうな気がするんだよな」
「どんな意味があると思うの?」
「普通だったら、関西支社を出すのに、参考になる話を謙二から聞き出すだけだったら、何も会社の内部まで見せる必要はないと思うんだよな?」
「私もそう思う」
「だから、お父さんは別なことを考えているんじゃないかなあ。俺も一緒に聞いといてくれって言ってたのに、急に変更したろう?」
「そう言えばそうよね、謙二さんと二言三言会話を交わして、急に態度が変わったわよね。悟さんがいたら、都合の悪い事でもあるのかしら」
「俺が思うに、俺がこの前、弟のことをお父さんに語ったろ?」
「ええ」
「恐らくお父さんは、俺の話がほんとなのかどうかを、実際に弟にあって判断しようと思ってたのじゃないのかなあ」
「ということは、悟さんの話を信用していなかったということなの?」
「いや、そこまではないとしても、実際に会うまでは確信が持てなかったのだと思うよ」
「なるほど。で、今日初めて謙二さんに会って、確信が持てたって訳ね? だから、悟さんは立ち会わなくてもいいと言い出したんだ」
「ま、そういうことだろうな」
「ったく、都合のいいことばかり言って、呆れてものが言えないわ」
「いや、俺はそうは思わない。お父さんの中で、別な何かが急に動き出したような気がするんだよ」
「別な何かって?」
「今は分らない。だから、謙二と二人きりで食事をしながら、何か探りを入れてみようと思って、さっき、ああいう言い方をしたんだよ」
「あ、そうだったんだ、……女はバカね。表面のことばっかりしか考えられないんだから」
「いや、そうでもないよ。……アキな」
「はい?」
「これはね、もしかしたら、家族全員が絡んでくる大異変に発展する可能性があるよ」
「悟さん、大異変だなんて脅さないでよ。そうでなくても心臓が弱いんだから、私」
「あはは、良く言うよ。俺はアキの心臓の強さにぞっこん惚れてんだから」
「あら、誉めてるの? けなしてるの? どっち?」
「決まってるじゃないか誉めてるんだよ。男ってな表面では強そうな顔や素振りをしていても、惚れた女には弱いってことさ。……アキの心臓の鼓動を聞くと、安心して眠れるってことを言いたかったんだよ」
「ふふ、そうだったの? じゃあ、許してあげる。……話が横道にそれちゃったじゃないの。……どんな大異変になると思ってるの?」
「俺の勘と、謙二から探り出したことをくっ付けると、何かが出てきそうな気がするけど、今は分らない」
「興味ある話ね。今日中には大体分るのね?」
「多分な、乞うご期待というところだな」
「じゃあ、私は食事の支度に掛ります。テレビでも見ててね」
「分った」
腕時計は十一時を指していた。誠一郎と謙二が部屋を出て行ってから既に二時間近く経っている。何を話しているのだろう。少し気になりだした。目はテレビに向いているが、頭は違う方向を向いていた。アキがコーヒーのお替りを運んできた。悟の顔を見て微笑んだ。
「弟さんのことが心配なのね。顔に書いてあるわよ。大丈夫、もうすぐしたら、二人とも笑いながら帰ってくるわよ」
悟はアキの顔をジッと見て小さな声で言った。
「アキ愛してるよ。……大好きだよ」
「まあ、嬉しいわ、……でも、どうしたのよ」
「アキの心臓が欲しい」
「私の心臓? ああ、分りました。今、誰も見てないからいいわよ」
アキは周りを見回して悟の隣に腰をおろし、悟の手を胸に当てた。
「感ずる? 心臓の鼓動。……あら、こっちの方がドキドキしちゃって、感じてきたじゃないのよ、……もう」
「あはは、もう大丈夫だ。落ち着いた。安心したよ」
「もう少しいいわよ」
「これ以上触ってると、アキをソファに押し倒したくなるから、……ヤバいよ」
「ふふふ、じゃあね、もう少ししたら食事の準備が整うから、リコにお父さん達を呼びに行かせるからね」
アキは嬉しそうに台所に消えた。
暫らくして、誠一郎と謙二がリビングルームに姿を現した。二人ともニコニコしていた。謙二は悟の横に誠一郎は前のソファに腰を下ろした。
「やあ悟、待たせてしまったな。お蔭でいい話になった。さすがにお前の弟だ。頼りになるな」
「そうでしたか、それは良かった」
そう言いながら悟は、横の謙二の方を振り向いた。謙二は頷きながら悟の顔を見た。嬉しそうな顔をしていた。
「さあ、食事の用意が出来たわよ席に着いてください」
母典子の声が聞こえてきた。
「オー、もう昼飯か。少し早いな。謙二君、さあ、飯でも食おうか」
誠一郎はすっかり謙二のファンになったみたいである。謙二の肩を押しながら、ニコニコした顔で食卓に着いた。
「謙二さん、お口に合うかどうか分りませんが、田舎料理です。遠慮なくね。お代わりもして頂戴ね」
「はい。ありがとうございます。……わァー、美味しそうですね、……では、遠慮なくいただきます」
謙二は味噌汁から口にした。みんなが注目した。特にリコは、味のことで謙二が何というか気になった。
「見られると何だか照れますね。……いやァー、美味しい味噌汁ですね、おふくろの味がします。ありがたいなあ」
謙二の素朴な語り方には実感がこもっていた。そのしぐさをジッと見ていた父の誠一郎は、何とも言えない優しい目つきをしていた。
「お父さん、謙二さんとの話はもう終わったのですか?」
アキが気にしていたことを切り出した。
「そうだな、いろいろあったが、今日のところは終わった」
「いろいろあったのですか?」
「あった。だが、この謙二君は大した男だよ参ったよ」
「悟さんとどうでした」
「いやはや甲乙付け難い頑固者だね」
「頑固者?」
「そうだ。実に頑固者だ、アッパレな武士道だな」
「えっ、武士道? ですか?」
リコが口を挟んできた。
「そうだ。悟の時も思ったが、この二人は、完全に薩摩武士の血を引いてるな。ほんとにたまげたよ」
「お父さん、今日のところはと言ったけど、またの機会があるってことなの?」
リコは聞かずにはおれなかった。こんな機会は、何度あっても大歓迎ですと言わんばかりである。アキが笑っていた。
「ま、そういうことだが、食事を済まそう」
誠一郎は何故か話を外らかした。あまり詳しく語りたがらなかった。
「ほんとに美味しい料理ですね。これは誰が作られたのですか?」
アキがリコの顔を指差した。
「リコ、あ、ごめんなさい、真理子のことをリコと呼んでいるんです。良かったらそう呼んでください。リコが、どうしても謙二さんに食べて貰いたいと聞かないものですから。これはリコの作品です」
謙二の前に並べられた食事を指してアキが説明した。
「ほんとですか? いやァー、大した腕前ですね。何処か料理教室でも通ったのですか?」
「いえ、母と姉に教わりました。褒めていただいて、とっても嬉しいです。……ありがとう。……お代わりしてください」
リコはもう大変な喜びようだった。アキも悟も二人の様子をほほえましく思った。父の誠一郎も母の典子も、頷きながら二人の会話に耳を傾けていた。
謙二は、リコが作った料理だと聞いて、リコを意識せざるを得なかった。こんな美味しい料理を、毎日食べられたら最高だろうなと思った。田舎に帰った時ぐらいしか美味しい料理は口にすることが出来ない。都会の味気ない料理にウンザリしているだけに、目の前の料理の美味しさは特別な意味合いを持って感じた。
「三度三度の食事を、美味しくいただけることほど幸せなことはないよな。何事にも代えがたい至福のひと時だからなあ。ありがたい事だよな」
悟がしみじみとした口調で話した。ふっと小さい頃の事が頭をよぎった。
「……」
謙二も同じ思いに違いないと悟は思った。
「……ご馳走さまでした。何だか尾を引きそうな味でした。ありがとうございました」
「また遠慮なくいらしてください。……と言っても神戸からじゃあ無理ね。遠いわね」
アキが気遣った。リコもやっぱり神戸は遠いなあと思った。
「そうですね、いえ、気持ちだけ頂いていきます。ほんとにありがとうございました」
謙二は腰を折り曲げて深く頭を下げた。
悟と謙二は、食後近くの喫茶店に足を運んだ。
「すまなかったな、思わぬことになってしまって」
「なーに、思わぬことが起るのも世の常だから何ともないよ、却って面白かったよ」
「全フロアを見て回ったのか?」
「そう。全部見た」
「どんな印象だった?」
「そうだなあ。改善しなければならないところが山ほどあるって感じだな」
「へェー、そんなにあるのかよ驚いたな」
「どっちかというと、社長のワンマン会社という印象だったけど、それではこれからは駄目だよな」
「うん。同感だな」
「社員全員の意見を吸い上げて営業戦略に生かすやり方でないと、同業他社にとても太刀打ちできない」
「それには優秀な人材がどうしても必要になってくる」
「そこなんだよ。優秀な人材がいるかどうか知る由はないが、社長自身が、その辺の認識をどの程度持っているかということだろうな」
「なるほどな。その考えを社長に言ったのか?」
「一通り説明を受けながら、見終わった後、受けた印象を聞かせてくれと言われたから、いろいろ率直な意見を言った」
「で、社長の反応は?」
「社長としては、受けた印象を聞かせてくれとは言ってはみたものの、俺みたいな若造に実際にズケズケ言われて、最初は面白くない顔をしていたけど、俺が会社を一流にしたいのなら、会社の膿に目をそむけず改善していくことが、どうしても避けて通れない事ではないのでしょうか、と言ったら、痛いところを突かれたというような顔はしていたけど、暫らく目を閉じて、何かを決断した感じだった」
「そうか、何を決断したんだろうな。謙二はどう思った?」
「ちょっと分らないな。俺も今日初めて社長に会った訳だし、全てを知っている訳じゃないから、深くは語れないしな」
「それはそうだよな。そっかあ、社長もいろいろ悩みがあるのかもな」
「それは俺も感じた。相当深い悩みを抱え込んでるんじゃないのかなあ。あの顔は」
「こんなことを謙二に話していいか分らないが、役員間でもいろいろあるみたいだしな」
「こんな小さな会社で、そんなことがあったら取り返しのつかないことになるぜ。早く何とかしないと、競合他社にしてやられるばっかりだよ」
「そうだよな。まず足元をしっかり固めないと、矢も鉄砲も相手に当たらないよな」
「そういうことだね」
「さっき食事の時、社長が、謙二との間でいろいろあった、と言っていたが、何かあったのか?」
「今話した件もそうだが、関西支社の設立の件があるんだってな」
「そうなんだよ。で、謙二にいろいろ話を聞きたいとか言ってたなあ」
「これまで社内で随分と長い時間を掛けて、関西地区の情報を調べ上げたようなんだよな」
「うん、聞いた」
「で、俺が関西地区に、そこそこ顔も利くだろうし実績もあるから、是非意見を聞かせてくれと言われんだよ」
「具体的にはどういうことだ? 仕入先とか、営業をかける相手は何処がいいかとかいう意味か?」
「うーん、少し違うけど、まあそんなとこだな」
「謙二の会社と似たような業種と俺は思っていたけど、どうだった?」
「業種としては、貿易という括りをすれば似てるけど、営業品目は似て非なるものだな」
「そうか。営業品目が違えば、仕入先とか営業をかける相手は自ずと違う訳だから、相談も何もないだろう」
「ところがそうでもないんだよ。確かに俺の会社とは、営業品目は似て非なるものだけど、仕入先とか営業をかける相手となると、同じ相手先となる可能性も大いにあるんだよ」
「なるほど、分る、分る。そうなると、その情報を教えるとなると……」
「そうなんだよ。産業スパイそのものとまではいかなくても、その類になってしまうだろう? 会社を裏切ることになるから、それは絶対に、死んでも出来ないと言ったんだ」
「そしたら、社長は?」
「そこを何とか曲げて頼めないかと必死だったよ」
「うん、それで?」
「もちろん、社長として、必死にならざるを得ないということは良く理解出来るんだが、出来ることと出来ないことが世の中にはあるからな。というより、俺の信条として、許せるものと許せないものがあるからな。そこで、失礼とは思ったんだが言ってやった」
「おまえ、変なこと言ったんじゃないだろうな。何と言ったんだ」
「社長の会社の社員に、よその会社の社長が同じようなことを要求したら、社長はその社員を許しますか? 許す筈がないですよね。もしそんなことをしたら、その社員は即刻首になりますよね。ということは、私も今の会社を首になりますよね。解雇ということになりますよね。それは、今の私には受け入れられません。ですから、これ以上お話しできません。帰らせていただきますって言ったんだ」
「ええーっ、お前バカだなあ、そこまで言ったのかよ。もうちょっと言いようがあったろうに」
「そう思ったんだが、社長は、物の本質が分ってないと思ったもんだから、つい言ってしまった」
「社長は怒ったろう? 凄い剣幕だったろう?」
「そう思うだろう? 俺も覚悟して言ったんだ。兄貴の手前もあるしな。もしかしたら、俺が失礼をしたことで、兄貴にもそれなりの影響があると思った。最悪、あの社長のことだから、婚約解消とか言い出すんじゃないかと、それも考えた。一瞬、兄貴には悪いなあと思った」
「ほォー、そこまで度胸決めたのか」
「だが、一方では、そんな愚をしでかす社長ではない筈だという思いもあった」
「で、どうなった?」
「ところが、驚くなかれ、社長は怒るどころか、にっこり笑ったんだよ」
「笑った?」
「そうなんだよ。そしてな? こう言うんだよ。お前たち兄弟は、実に大したものだ感服した、……とな」
「それは、俺も言われた経験あるぜ」
「やっぱりなあ。社長は、俺がどういう返事をするか試したんだよ」
「なるほど。したたかだな」
「それに、こんなことまで言い出すんだよ。この際、首になったらどうなんだ? 俺が死ぬまで面倒見るよ、って、……どう思う? 普通初対面でいきなりそんなこと言うか?」
「あはは、自分が先に死んでしまうのに、よく言うよな」
「だろう? 俺が死ぬまで生きていたら、お化けだよ」
「あはは、だよな」
「そこで、大笑いになって話が続いたんだ」
「案外社長は、お前に今の会社を辞めて、来てもらいたいと思ってるんじゃないのか?」
「いや、それはないと思うけど、兄貴は俺のことを、社長に相当吹き込んだんじゃないのか?」
「何でだよ。社長が、お前のことをどういう男だって聞くから、ありのままを正直に言ったまでだよ。仕事のことは俺が知ってる範囲で話したまでだよ。それが悪い事か?」
「いや、そうは言ってないさ。余りにも俺のことを良く言うものだから、それは相当な買い被りですよと言ったんだが」
「それで社長は?」
「俺もだてに会社のトップになってないよ、こうして二時間近くも話を交わせば、その人となりは充分理解出来るよ。その上で言ってるんだよだって」
「うんうん、なるほどな。理屈だな。で?」
「宿題を出された」
謙二がポツリと言った。
「宿題?」
「うん」
「どんな?」
「謙二がって、いきなり呼び捨てに言うんだよな」
「あははは、お前を完全に心から許した証拠だよ。もう身内になったようなもんだよ」
「そっかあ、そういうことか、ま、悪くはないな」
その時、悟の携帯が鳴った。ディスプレイにアキとあった。
「もう、そろそろいいかしら?」
「そうだな、ごめんだけど、あと十分後に来てくれるかな?」
「はい。分りました」
「誰?」
謙二が誰からの電話だと聞いてきた。
「アキとリコが、一緒にコーヒー飲みたいんだってさ。十分後にここに来るからそのつもりでな」
「そっか。うんいいね」
「で、その宿題とは?」
「それが奮ってるんだよ。謙二、お前が社長になったつもりで、関西支社設立の骨子をまとめてくれってさ」
「嘘だろう? そんなこという訳ないだろう? 社員でもないのに」
「俺もそれを言ったんだよ。そしたら、社長何と言ったと思う?」
「産業スパイにならない範囲で、関西支社設立に関する意見を、報告書としてまとめてくれ? か?」
「兄貴、さすがだな、そのものずばりだよ」
「で、お前は何と返事したんだ」
「そう言われればOKせざるを得ないだろう? 社長は意外としたたかで策士だぜ、兄貴」
「あはは、俺はとうに見破ってるさ。憎めない策士だな、ちょっと策に溺れてしまうところも無きにしも非ずだがな」
「うんうん、そうかもな。……ま、そういうことで終わったということです」
「そうか、で、さっき食事の時リコに尋ねられて、社長が、今日のところは終わった、という言葉になったという訳だな? まだまだ続きがあるってことだ」
「そういうことだね」
「で、その報告書は、いつまでに提出することになったんだ?」
「今年の秋に設立予定だそうだな?」
「そうみたいだな」
「三月末の役員会に計りたいから、遅くとも二月末までにということだった」
「時間が余りないな?」
「そうなんだよ、ま、全力で書き上げるしかないな」
「そうか道理で……。何だか急いでいる様子だったからなあ」
「そうかもな」
「で、書き上げた報告書はどうするんだ? 神戸まで取りに来てもらうのか?」
「いや郵送することになると思う」
「あ、そうかなるほどな。だけど考えてみたら、お前を連れてきたばっかりに、宿題まで出される羽目になってしまって、悪かったなあ」
「最初俺も、何で俺がそこまでしなきゃならないんだと思ったんだけど、これも天命だと思って、役に立つかどうかは自信はないが、引き受けることにしたんだよ」
「なるほどな」
「でも、考えてみたらありがたいことだよな、こんな若者の意見を聞いてくれるなんて、他の会社じゃあり得ないよな」
「そうそう、だから、見かけによらず大物の社長かも知れないぜ、あの社長」
「そうかもな」
「謙二頼みがあるんだがな」
「うん、何?」
「十四時から養成講座があるんだよ」
「養成講座? 何だよそれ」
「時間がないから詳しくは話せないんだが、リコが明日の十日から新入社員として働くことになったんだよ。で、リコにとっては初めての経験になる訳だから、前もって教育しておいた方がいいだろうということになって、俺が担当することになって、だいぶ前から養成講座と銘打ってやってるんだよ。ロールプレイングなんかをやってきたんだよ」
「お、そうか。いいことだな。で、頼みって言うのは?」
「今日がとりあえず最後になるんだけど、お前も、後ろの方で見ていてくれないかなと思って」
「えっ、俺がかい?」
「そうだ。もう最後の講座だから、基本的なことの復習みたいなもんだけど、終わった後に、お前の意見を聞きたいと思ってな」
「そうか。俺もさんざん教育されたからなあ。あれはきつかったなぁ。ほんとに辛かった。ま、あのお蔭で今日がある訳だから、ありがたい教育だったんだけどな」
「何といっても、最初の教育ほど大事なものはないからな。しかも身内となると、社員になった時、社内で変な風になってもいけないからなあ、結構神経使うよな」
「なるほど。言われてみればそうだな。身内となれば、普通の社員を教育するのと、また別な意味でやり難いところもあるかもな。うんうん、分る、分る」
「リコも最初の頃から比べると、見違えるようになってきたよ。最初の頃は、ロールプレイングの時に泣き出してなあ、困ったものだよ。それも、時間の経過とともにマスターしてな、今じゃ何も言うことなくなった。結構頭がいい子だから吸収力は凄いな」
「そうなんだ、うん、分った。後ろで見ておけばいいのだな?」
「うん。そうしてくれるか? それで俺が頃合いを見てお前に振るから、二つほど答えてもらいたいんだよ」
「えっ、見るだけじゃなくて、何か答える訳? しかも二つもかい?」
「一つは新入社員の心構え」
「えっ、それはやったんじゃないの?」
「もちろんやったさ。お前が語るところに意味があるんだよ。……分るだろ?」
「兄貴はやっぱりさすがだよ。うん。分った。……二つ目は?」
「リコには、一年以内に英会話をマスターするように言ってあるんあるんだよ」
「英会話を? ほォー、なるほど。読めて来たぞ」
「お前は英会話がペラペラだから、英会話が出来ない俺が言うより、お前から言ってもらった方が説得力があると思うんだよ」
「何を言えばいいのかな?」
「英会話を早く習得する方法だよ」
「なるほど。経験者の俺が言えば、より説得力があるということだな?」
「そういうことだよ。頼むわ」
「よっしゃ。分った」
謙二は微笑みながら、納得顔で悟に応じた。
「それと」
「まだあるの?」
「これはどう思うかなあ、……復習の意味で、謙二とリコがロールプレイングするっていうのは」
「エエーッ、俺とリコさんと? よしてくれよ。今日初めて会ったばかりなのに、出来る訳ないだろう?」
「いや、お前だったら出来ると思って言ってるんだよ。今日、社内をくまなく見て来た訳だから、お前なりに実務の場面はお手のもんだろう? それに、俺とリコと違って、お前とリコがやることで、また新鮮な気持ちになって、より効果があるような気がするんだよ。今日初めて会ったばかりで、やりにくいかもしれないが、リコの将来のことを思って頼むわ。……なっ?」
「うーん。主旨は分ったけど、困ったなあ。上手くやれるかなあ」
「大丈夫だよ。お前のことだ、上手くやれるよ。……シチュエーションは任せるから、いいだろ?」
悟は謙二とリコとをロールプレイングさせることに、ある大きな意味合いを持たせていた。
「せっかくの兄貴の頼みだからなあ、うん、ま、やって見るか。何かの座興にはなるだろう。……分った」
「ありがとう。講座の最後の最後に俺が振るからな? そのつもりでな? 後は任せる」
「分った。……それにしても、兄貴も大変だなあ。自分の仕事も忙しいっていうのに」
「なーに、これも天の命令だよ。それに、やればやるほど、新鮮味があって面白いよ」
「なるほどなあ。目の前の一つ一つを確実にこなしていく。実に兄貴らしいな。いやいや、恐れ入りましたでござる」
「あはは、これで一件落着~」
タイミング良くアキとリコが入ってきた。悟と謙二は、四人掛けのテーブルに向かい合って座ってた。だから、隣の席が空いていたことになる。アキは悟の隣に、リコは謙二の隣に座ることになってしまった。リコは恥ずかしそうにして、遠慮がちに謙二の隣に座った。
「もう、お話は済んだの?」
アキが悟の顔を見ながら言った。
「丁度今終ったばかりだった」
「そう、それは良かった」
「その後、お父さんの様子はどうだった?」
「ええ、珍しくずーっとニコニコ顔だったわよ。何かあったのかしら」
「どうも、謙二との間に密約が交わされたみたいだな」
「密約ですか? どんな密約かしら」
「今は聞かないほうが花というものだよ。いずれ近いうちに明らかになる。それを待つのも楽しみじゃないか」
「そうね、そうだわね。……謙二さんお疲れじゃありません? あんな父親ですみません」
「謝ることなんかちっともありませんよ。私も随分勉強になりました。お伺いして良かったと思っています」
「そう言っていただくと嬉しいわ。お兄さんに似て優しいのね」
「あはは、兄貴の優しさは大きくて天下一品ですが、私はもっと見習わなければと思っているところです」
「まあ、ご謙遜を。……ところで悟さん、養成講座は今日でとうとう終わりですね」
「そうだな。終わりとなると、少し寂しい気もするけど、リコが見違えるようになってくれたから、ま、成果としてはあったと言えるかな?」
「言えるかなどころじゃないわよ。リコの変化の凄さにびっくりしているところなのよ。ねえ、リコ。……黙ってないで何か言ったら?」
「あ、はい、お兄さんのお蔭で大分自信がつきました。ありがとうございました。これからは、実戦で恥じないようにもっともっと頑張ります」
「リコはもう大丈夫だよ。もう何も言うことはありません」
「今日はどんなことをするんですか?」
「今日は最後の最後だから、初心に戻って、基本的なことの復習をして終わりにしようかな?」
「はい。分りました。よろしくお願いします」
「今日は早めに終わって、駅に行きがてら、またここに来ることにしようか。お別れ会をしよう」
「お別れ会ですか? お兄さん、もうここには来ないのですか?」
リコが淋しい顔になった。
「違うよ。養成講座の解散会だよ。俺はいつもの通り来るよ。隣の鬼が牙をむくからな」
「コラッ、鬼とは何よ鬼とは」
「だって、赤鬼と青鬼だろ?」
「ふふ、さすがお兄さん、うまい」
「何だい? その赤鬼青鬼って」
謙二が口を挟んだ。
「あ、そうか。後でリビングの壁に貼ってある写真を見たら分るよ」
「嫌だー、恥ずかしい。謙二さんお願い見ないで」
リコが謙二の顔を見ながら、恥ずかしそうな声で言った。
「そう言われたら、なおさら見たくなるのが人情というものでしょう? 見させていただきます。じっくりとね」
「ウァー、早く帰ってはがそうかなあ」
「ま、仕方がないね、諦めるんだな。何といっても、リコが自慢のデジカメで撮った写真展だからな。個展みたいなもんだよ」
「そうよ、謙二さんにもじっくり見ていただいて、来年来てもらった時の参考にしていただいたら?」
アキの意味ありげな言葉に、リコは黙り込んでしまった。
「おーー、それはいい考えだな。リコ、ディレクターとしては、謙二はどういうスタイルかな?」
「もう、お兄さんたら、急に言われても思いつく訳ないでしょう? お姉さんみたいに頭が良くないんだから」
「何言ってるんだよ、アキ姉さんはな、いつも俺に言ってることがあるんだぜ、知りたいか?」
「えっ、ほんと? どんなこと? お姉さん何と言ってるの?」
「あのな、リコの頭の回転にはついて行けないってさ」
「嘘だあー、そんな筈絶対ない、ない。ありっこない。もうちょっと上手な嘘ついてよ、お兄さん」
「嘘なもんか、な、アキ」
「そうよリコ。養成講座の最初の頃は、確かにリコも大したことないわ、まだまだねと正直そう思っていたの。ところが講座が進むにつれて、リコの頭の回転にはとてもついて行けないと思ったの。そのくらい最近のリコは凄いわよ。これほんとよ」
「えっ、ほんとなの? だったら嬉しいなあ。リコには、お姉さんよりも優れたところなんか一つもないんだもの」
「リコは、どうも自分のことが良く分ってないみたいだな」
悟がリコの顔を見て言った。
「えっ、お兄さんどういうこと?」
「リコには、アキにはない天性の輝きがあるってことさ。アキが俺にな、そっと打ち明けてくれたことがあるんだよ」
「リコのことで?」
「うん。そうだよ」
「何々、何なの?」
「それは秘密だな。機会があったらアキに教えてもらうといいよ。それを聞いて俺も頷いたぐらいだから」
「そう、何だろう」
「言いたいことは、リコには素晴らしい才能が満ち溢れているってことさ。自信を持ってもいいと思うよ」
「言われると何だか嬉しけど、自分では分らないわ。……でも、ありがとう」
リコは明るく笑った。実に魅力的な顔である。謙二はリコを見て、今まで感じたことのない新鮮な驚きを感じた。
「で、ディレクター、謙二のコスプレは?」
「またそこに戻ったの? お兄さんて絶対忘れないのね」
「結構しつっこいだろ? 性分だから諦めるんだな」
「謙二さんのコスプレ? うーんそうねえ、トラのぬいぐるみに、大仏様の仮面はどうかしら」
「あは、面白そう、また来年が楽しみね」
アキが乗ってきた。
「謙二さん神戸から来れるの? 毎年田舎に帰ってるんでしょう?」
リコが謙二を見て言った。
「そうね、多分、田舎に帰ると思うからその話は無理かも」
「やっぱりそうよね、……ああ残念」
「でも、トラのぬいぐるみを着て、大仏様の仮面を被って何をするの?」
謙二が理解し難い顔をした。
「餅つき」
「へェー、餅つき? 面白そうだなあ」
「でしょう? 後で写真見たら分るけど、ギネス級の面白さよ」
「そうなんだ。写真見るのが楽しみになってきた」
養成講座が始まる少し前に家に戻った。
十四時になり最後の養成講座が始まった。場所は会社の会議室である。
後ろの席に両親とアキとそれに謙二が加わった。リコはいよいよ明日の十日から社員として働くことになっている。しかも今日は、後方で謙二が見ている。いつもと違う雰囲気に、いやが上にも緊張が高まってきた。講座の内容は、基本的なことの再確認をしながらの復習であった。予定の講座を終わった。
「えェー、一応予定の講座は終了しました。リコは長い間ご苦労さんでした。大変だったろうけど良くついて来てくれました。リコの頑張りに頭が下がります。……どうでしょうか? リコに拍手をお願いしたいのですが」
悟は後ろで見ている両親たちを促した。みんな大きく頷きながら力いっぱい手を叩いた。
「では、リコに講座の感想をも兼ねたご挨拶をお願いします」
リコは急に言われて驚いた。全く用意していなかった。しかし、慌てる素振りはなかった。緊張した顔ではあったが、微笑みながら黒板の前のテーブルの方に歩を進めた。
「ご挨拶をと突然に言われまして少し戸惑っています。言葉足らずのところがあるかもしれませんがお許しください。エェー、まずは、私の為に長い間鍛えていただいた悟お兄さん、あ、失礼しました、早川悟先生に厚くお礼申し上げます。ほんとにありがとうございました」
リコは悟の方を向いて深く頭を下げた。悟の顔は嬉しそうだった。リコは続けた。
「この歳になるまで、世間知らずで、何一つ分っていなかった私が、会社の一員となり仕事をするなんてことは、希望としてはあっても現実問題としてはあり得ない、遠い幻想としか思っていませんでした。思い切ってお父さんに相談しなさい、という先生のアドバイスをいただき、アメリカに出張するお父さんに、飛行機の中で読んでもらう為に手紙を書きました。そして、お父さんから思ってもみなかった許可が出た時は、心臓が止まるくらいにびっくりしました。涙が出るくらいに嬉しく思いました。お父さん、ほんとにありがとうございました」
リコは父親に向かって深く頭を下げた。両親は目を細めて頷き、成長した娘の語りに聞き入っていた。リコが続けた。
「今後は、教えていただいたことを、一つ一つ実戦で実行していきたいと思います。そして近い将来に、先生や両親やアキ姉さんから良くやった、と、褒められるような自分になりたいと思っています。必ず期待に応えられるような人間になりますので、どうか、今後ともご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」
リコは、みんなに向かって深く頭を下げて席に戻った。期せずして大きな拍手が起こった。立派な挨拶だった。えっ? これが私の妹? 嘘でしょう? アキは信じられないと言う顔をした。両親も同じ思いだったに違いない。謙二は一人微笑みながら大きく頷いていた。なかなかやるじゃないか。
「それでは、せっかくですから、来賓の方にもお言葉を頂戴致します」
来賓の方々と来たか。もうこの男憎たらしい。
「じゃあ、まず、お姉さんの亜希子さん、どうぞ前へお願いします」
あら、全然心の準備が出来ていません。えーい、なるようになれだ。
「リコ、卒業おめでとう。良かったね。今のリコの話を聞いてて、えっ、これが私の妹? と思いました。まるで別人じゃないかと錯覚するくらいにびっくりしました。私たちの見えない所で、かなり学習したのではと推察しました。リコの努力に頭が下がる思いがしました。今の気持ちを忘れずに頑張ってね。いつまでも応援するからね。それと、悟さんありがとう。心から感謝しています。悟さんの発案でこういうことになり、リコが日に日に成長していく姿を見て、もしこういうことがなかったらと思うとぞっとします。そう思ったら、何とお礼を言ったらいいのか分りません。ただただ、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。……以上です」
大きな拍手が起こった。
「ありがとうございました。続いて、お母さんお願いします」
母の典子は、もうこういう雰囲気にだいぶ慣れてきた。初めての事ばかりだが何だか楽しかった。もっと若い時にこういうことがあったら、もっと良かったのにとすら思うことだった。
「まずは悟、月並みだけどありがとう。私には会社の仕事のことは皆目分りません。でも娘のリコの、もうついこの間までのリコではない立派な姿を見て、目を疑ったぐらいです。まだまだこれからですし先は長いけど、リコにとって第一歩が力強く踏み出せたのではと思って、とても嬉しく思います。人間、手を差し伸べられる範囲には限界があります。後はリコが、自らの手で自らの頭脳で、しっかりと人生を歩んで行くより方法はないと思います。そうなるように心から願っています」
母の優しさあふれる話だった。
「続いて、お父さんお願いいたします」
父、誠一郎が中央に立った。
「エェー、実はこの養成講座で一番感動したことがあります。それは何かというと悟の熱意です。最初リコが泣き出した時、そこまで厳しくしなくてもと思いました。だが、悟は手を抜くどころか、これでもかこれでもかと、リコをいじめ抜きました。親としてリコが可哀想に思ったことも確かにありました。しかし、リコも耐え抜きました。我が子に、そこまでの忍耐力と負けん気があったなんてとても信じられません。
暫らくして、リコの生き生きした行動やハキハキした語り口を見て、正直、自分を恥ずかしく思いました。実に情けない親だったと痛感しました。リコの能力を見抜けない親が、会社の社長でございますと、威張っている自分の姿を見て、穴があったら入りたい心境でした。
実はこの講座を通して、一番勉強させてもらったのは自分だと思っています。会社ももちろん大事だが、その前に親としての考え方や、家族の絆、人間愛、人の心に寄り添って生きて行くことの大切さなど、実に多くのことを学びました。
人間は愛情を注げば注ぐほど期待すればするほど、その大きさに応じて大きくなるものだと思いました。そういった意味で、会社にとって、人材の育成ほど大事なものはないと思うと同時に、早急に、人材育成に向けたプログラムを作らなければと思った次第です。
悟、ありがとう。ほんとにありがとう。君のお蔭で何よりも家庭がとても明るくなりました。淀んでいた空気が、爽やかに吹き抜けるようになって風通しが良くなりました。食事がとても美味しくいただけるようになりました。お母さんがとても愛おしく思えるようになりました。もう挙げたらきりがありません。あとは、この教訓をいかにして実践に移していき、成果を上げるかです。
長くなりましたが、語り尽くせないほど嬉しい事ばかりです。ありがたいことばかりです。
最後にリコのことですが、せっかくここまで指導していただきながら、今後、リコが思ったほど成長しないようだと、完全に社長である私の責任です。そうならないように、私も初心に帰って頑張ります。悟、これからも宜しくな。……ほんとにありがとう」
シーンとして聞いていたみんなが、悟の拍手を契機に一斉に大きな拍手をした。
「おとうさん、ありがとうございます。それでは最後に、弟謙二に今日の感想などを述べていただきます。謙二には出来れば、謙二の新入社員の時のことだとか、英会話をどうやったら早く習得出来るかなども含めて、話をしてもらえばありがたいです。……じゃあ、宜しく」
両親やアキやリコは、思わぬ展開に驚いた。アキは、常識では判断できない悟のやり方には慣れてきたが、いつも新鮮だった。謙二はゆっくりと前に進み出た。リコは謙二の顔に視線を集中させた。
「エェー、思わぬ展開になり正直戸惑っております。その前にお礼を申し述べたいと思います。
私はもうすぐ東京に戻らなければなりません。今朝からお邪魔しているのですが、美味しい料理をご馳走になり、お父さまといろいろお話しさせていただきました。皆様の実に温かい心に触れて、ほんとにお邪魔して良かったと思います。と、同時に、こんな素晴らしい温かい家族に囲まれて、兄は何と幸せな男だろうと思いました。一日があっという間でした。後ろ髪引かれるような感動の一日でした。すっかりお世話になってしまいました。ありがとうございました」
謙二はみんなに向かって深く頭を下げた。
「さて、先ほどから後ろで見させていただきながら、私の新入社員の頃を思い出していました。私の会社は大きいと言うほどではありませんが、そこそこの規模の会社です。会社が掲げるスローガンに人材育成というのがあります。ですから新入社員の教育訓練は、筆舌に尽くしがたいくらいの厳しさでした。その厳しさに耐え、這い上がって来る社員しかまともな道は与えられないのです。
先ほどリコさんが泣かれたと聞きましたが、私も泣きました。何でこんなことをしなければならないのだと、寮に帰って壁や机を叩いて泣きました。挫折して会社を辞めていく社員もいました。人生に希望を抱いて入ってきた同僚たちが、その厳しさに耐えられず、私の前から次々と姿を消していきました。あれから相当な月日が流れました。彼らが今どうしているのか知りません。私は必死になって歯を食いしばって耐えました。そうしましたら、不思議なことが起きました。多分、自分の感覚がマヒしていたのだと思うのですが、厳しさが厳しいと思わなくなってきたのです。むしろ、楽しみや喜びに変わって行ったのです。私はその時何故か、自信めいたものを感じました。やっていけそうな確信みたいなものが芽生えてきました。
今ではお陰様で、重要な仕事を任されるようになりましたが、未だにその時のことは忘れないようにしています。自分という人間をとことん鍛え上げ、オーバーな言い方をしますと、自分は何のために生まれてきたのだとか、これからどうやって生きて行けばいいかなどの、気づきを教えてくれた訓練でしたから、いつまでも忘れないように心掛けています。
今日のリコさんのお話を聞いて、私の新入社員の頃と重なってしまいました。私の体験をお話しすることで、少しでもお役にたてばと思いお話しさせていただきました。リコさん、辛いこともあるかもしれませんが頑張ってください。あなたならきっと出来ます。期待しています」
大きな拍手が起こった。リコは嬉しさで胸がいっぱいになった。この時リコは、この人と一生を共に暮して行きたいと強く思った。
「それから、英会話のことですが、私は英検準一級の資格を持っています。TOEICは八百点台を取りました。日常会話や仕事上の取引会社との会話には全然不自由しません。
ではどうやったら会話が出来るようになるかと言いますと、……簡単です。英語を好きになることです。好きこそものの上手なれと言う言葉がありますが、英語が好きな人はグングン伸びます。逆に嫌いな人は絶対に伸びません。私の場合は、仕事をより有利に展開する為に、止むを得ずと言いますか、必要に迫られて英会話の勉強を始めたのですが、最初のうちは大変でしたが、段々好きになってきました。そうしましたら、徐々に会話出来るようになったのです。また、習うより慣れろと言う言葉がありますが、正にその通りです。
基本的には、実践で学ぶ方が格段に早く習得できます。出来れば、海外に社長が出張なさる時に、リコさんも一緒に同行されて勉強されれば、あっという間に習得できますよ。私の場合、海外出張はたまにしかありませんが、商社の出先機関には外人さんが一杯おりますから、しょっちゅう出かけて行って積極的にアタックしました。
ここでは語りつくせませんので、私が最初に思い立ったころから、実践で会話するようになるまでの記録や資料、それに教材などが、多分、まだあると思いますので、何かの参考になると思います。差し上げます。社長から頂いた宿題の報告書と一緒に郵送しましょう」
リコは謙二を凄いと思った。教材も送ってくれると言う。嬉しかった。
「以上、とりとめのない話になったような気がしますが、参考になれば幸いです」
誠一郎は、謙二の話を聞いて目を細めた。年は若いが、凄まじいエネルギーで、目の前の難関を突破してきた自信が満ち溢れていた。頼もしい人物の登場である。
「謙二、ありがとう。リコ、謙二の言うことは理解できたかな?」
悟はリコに顔を向けた。
「はい。とっても良いお話を聞かせていただきました。益々頑張ろうという気が起りました。ありがとうございます。教材なども宜しくお願い致します」
リコは謙二に向かって頭を下げた。謙二はニコニコしていた。
「えェー、いよいよこの講座も最後の最後になってきました。……ここで私からの提案です」
悟の話に謙二はいよいよ来たかと、半ばあきらめ顔で、運を天に任せるよりないなと腹をくくった。出たとこ勝負だ。
「今日初めて謙二が来てくれました。楽しいひと時でした」
みんな大きく頷いた。
「さて、謙二は今日帰ります。謙二が帰った後のことを想像してみてください。帰ってしまったら、今度いつ会えるか分りません」
悟に言われてみんな現実を知った。謙二は、兄貴は実に上手いこと持っていくなあと感心していた。
「そこで、私からの提案です。この講座の締めくくりに、謙二とリコによるロールプレイングをしていただきたいのですが、賛成の方は手を上げてください」
アキはびっくりした。まさかそこまで考えるか? 両親もさすがに驚いた。一番驚いたのはリコである。腰を抜かしそうになった。謙二とのロールプレイングのイメージが全く湧かなかった。お願いだから止めてよ。そんなこと出来ない。心臓が止まったらどうするのよ。ところが、リコの意に反して全員が賛成の手を上げた。そして拍手が湧き起った。
「リコの巣立ちに、実戦で鍛え上げた謙二とのロールプレイングで、花を添えることになりました。今一度、盛大な拍手で二人を迎えましょう」
再び大きな拍手が湧き起った。謙二は兄の巧みな持っていき方に、苦笑いせざるを得なかった。リコと謙二は完全にまな板の鯉と化した。アキは、リコが持ってきたデジカメをスタンバイさせた。
「シチュエーションは謙二にお任せします。……それでは、どうぞ」
謙二が中央に立った。
「急なことで、何をどうしていいか思い浮かびません。全部がもう既に経験済みなことばかりだと思いますので、ま、復習のつもりで気軽にやりましょうか。リコさん宜しくお願い致します」
謙二を目の前にして、リコは完全に緊張していた。胸がドキドキして、何が起こっているのか理解に苦しんだ。
「あ、はい、こちらこそよろしくお願い致します」
リコは度胸を決めた。もう、なるようになれと言う心境になった。
「えーとですね、まずは、明日十日に入社ということをお聞きしておりますので、朝礼の時、全社員に向かって自己紹介を兼ねた挨拶をしてもらいます。私が人事課長のつもりでリコさんを紹介しますので、その後続いてお願いします。……いいですね?」
「はい。分りました」
「それから次に、主任に取引先から電話が掛ってきました。私が主任の役をやりますので、電話の取次ぎをお願いします。兄貴、取引先の商社の担当者の役をお願いできますか?」
「取引先の商社の担当者の役だな、オーケー」
「そして、次の場面は、商社の担当者が来社しました。お通ししてお茶を出すシーンをやります。私が商社の担当者の役をやりますので、リコさんは受付の事務員になってください。……いいですね?」
「はい。分りました」
「次に、リコさんは社長秘書の役をやっていただきます。私が社長の役をしますから、アドリブでお願いします。何が飛び出してくるか分りませんから、覚悟しておいてください」
「エエッー、社長秘書ですか? アドリブですか? 出来るかしら」
「そうです。出来なかったら、出来るまで何度でもやっていただきます。……いいですね?」
「分りました」
「最後に、アメリカ人夫妻が社長を訪ねてきました。私が社長の役をします。……社長、あ、あは、ややこしいですね、お父さんとお母さん、すみませんがアメリカ人夫妻の役をお願いできますか?」
誠一郎は驚いた。良くあることだが、まさかここで出て来るとは。
「分った」
「お父さんは、英会話出来るんですよね?」
「そうだな、片言だけど日常会話なら何とかなるかな」
「分りました。アメリカ人夫妻が、社長の私を訪ねて来たという設定でします。私とお父さんと実際に英語で会話しますので、リコさんは良く見ておいてください。こういう場合の、アメリカと日本の習慣の違いというものがあります。その辺の違いについて、何となく理解出来ればいいと思います」
「私も何かするの?」
母の典子が心配そうに尋ねた。
「いえ、お母さんは、ただ黙ってお父さんの傍にいてください。何もすることはありませんが、笑顔だけは忘れないようにお願いいたします」
「はい。分りました」
それでは始めますと言って、謙二がリコに向かってロールプレイングを開始した。両親もアキも興味深く成り行きを見守っていたが、リコが実にスムーズにこなす姿を見て感心した。悟は頷きながら眺めていた。二人は楽しそうだった。リコは謙二と会話するうちに、だんだん余裕が出て来た。楽しくなってきた。朝礼の時の立つ姿勢や、視線のやり方、手の位置など謙二が実際にリコの手を取ったりしてアドバイスした。その度にリコの胸が舞い上がった。その表情を見てアキは微笑んだ。しめたと思うと同時に、悟はここまで計算に入れてると思った。憎たらしい奴だと思った。
商社の担当者から電話が掛って来たシーンは、商社の担当役の悟が、実際には余りあり得ないが、わざと悪態をついた電話をした。悟が考えた応用編である。リコは余りの悪態をついた言葉に、会話に詰まったり、メモを取るのに慌てたりした。謙二はリコの傍に行き、リコの手を取り受話器の取り方とメモ用紙の置き方など細かく教えた、そして、主任のデスクの前で、電話が掛ってきた旨の取次ぎの仕方を教えた。
商社の担当者にお茶を出すシーンも細かくチェックされた。腰を落として床に膝を着き、お茶を差し出すシーンでも、リコの手を実際につかんだり触れたりして教えた。悟も当然同じシーンを教えたが、謙二には予め、リコが正しいお茶の出し方をしても、もう一度確認の意味で手に触れながら丁寧に教えるように頼んでおいた。
社長秘書のシーンでは、社長役の謙二が厳しい社長に豹変した。あまりの謙二の豹変ぶりに、両親もアキもびっくりした。悟はニヤニヤ笑うばかりだった。やるじゃないか、もっとヤレヤレと言わんばかりである。当のリコは秘書役は初めての経験だった。誠一郎は、興味ありげに身を乗り出して見ていた。俺はそんなに厳しくないぞと思ったりした。と同時に、近い将来、実際にリコが秘書として同行する姿を思い描いた。リコも負けてはいなかった。これでもかこれでもかと、アドリブを投げかける社長役の謙二に、必死になって言葉を返した。二人とも汗が出て来た。
いよいよ、最後のアメリカ人夫婦の訪問である。誠一郎と謙二の会話を聞いて全員が驚いた。謙二はまるで外人だった。身振り手振りの話しぶりは、アメリカ人そのものだった。流暢な英語が響き渡った。リコは謙二の顔を見つめ、私もこのように英会話が出来るようになりたいと強く思った。
その時だった。アキがつかつかと謙二の前に歩み寄り、失礼と言って流ちょうな英語でしゃべり始めた。謙二はニタリと笑って受け答えた。そして、アキの顔を見ながら大きく頷き拍手した。アキは今度は、アメリカ人夫婦に向かって二言三言喋った。誠一郎は言葉を失っていたが、母の典子は、当たり前みたいな顔で、笑って成り行きを見守っていた。
突然起こった出来事は、大変な騒ぎになってしまった。まず、一番驚いたのは誠一郎だった。度肝を抜かして、今にも床に崩れそうになった。口を半開きにしてアキを見詰めた。
「お前は、いつからそんなに英会話が出来るようになったんだ?」
「通訳案内士登録証を受けてから、もう、丸三年になります」
「なにー、お前は俺にそのことを隠していたのか?」
誠一郎が凄い剣幕で怒りだした。三年といえば、その間に、アキも同行して海外に出張している。だが、現地でアキは一言も英語では会話しなかった。わざわざ高い通訳料を払っていることは充分分っていた筈なのに、何故だ。何故なのだ。
「はい。そうです」
「どうしてだ?」
雲行きが怪しくなってきた。誠一郎は、アキに今にも掴みかからんばかりの形相になった。
「お父さん」
母の典子が、たまりかねて誠一郎の前に顔を出した。
「私から説明します」
「何? お前はこのことを知っていたのか?」
「はい。知っていました」
「じゃあ、何か? もしかしたら、お前ら親子して俺を騙し続けて来たと言うのか?」
誠一郎は、典子を睨みつけて、ますます機嫌が悪くなった。
「お父さん、アキがどうして隠していたのかを、今ちゃんと説明しますから落ち着いて聞いてください」
「……」
誠一郎は、周りを見回して椅子に腰を下ろした。みんなも腰を下ろした。リコは、突然の出来事におろおろしていた。姉のことは何でも知っているつもりだったが、そうじゃなかった。ショックだった。しかし姉にとっては、そうしなければならない相応の理由があったのだと思った。
悟も、アキが英会話が出来るなんて、一言も聞かされていなかった。イブの前の日の家族会議の時、母の典子とアキの意味ありげな素振りに、何か秘密めいたものがあると睨んではいたが、このことだったのだ。騙されていたとは言えないが、面白くないのは確かである。だが、アキのことだ、何か考えることがあっての事だろうと思うと同時に、願ってもない展開になりそうで、そちらの方を喜んだ。
謙二はニヤニヤしながら成行きを楽しんでいた。
「お父さんあのですね、アキは、お父さんから養子縁組のことを聞くようになってから、急に不機嫌になりましたよね」
「そうか? そんなこと、俺がいちいち知る訳ないだろう」
「……話聞いて。……その話が出るようになってから、アキの心が変わったの。ことごとく、お父さんに反発し出したの。それでも、お父さんの娘ですから最悪のことを想定してたのね、アキは」
「最悪の事って何だよ」
「養子縁組のことよ」
「それが、そんなに最悪の事か?」
「アキにとってはそうなのよ」
「うん。それで?」
「アキは、一時自分の思いを諦めた時があったの。これも、私の人生かも運命なのかもって。お父さんは気付かなかったかもしれないけど、傍で見ていて、それはそれは可哀想なくらい落ち込んで、食事も喉を通らないくらいだったの」
「……」
「それでも、この子の良いところは、もしそうなったらそうなったで、お父さんに反発しながらでも、考えた事があったのね。それは、娘としてお父さんのお手伝いが出来るようにならなければいけない、と考えていた時に、何かの時に、馬鹿高い通訳料を会社が支払っていることを知ったのね」
「うん。それで?」
「いろいろ考えたのだと思うわ。ある日、アキから私に相談があったの。そう、あれは五年くらい前かしらね」
典子はアキを見た。アキが頷いていた。
「アキが通訳士になるって言い出したの。通訳士って、とっても難しいでしょう? でも、なるって聞かないの。その代り、合格して通訳案内士登録証が来ても、絶対に誰にも話さないでと言うの」
「……」
「どうして? って聞いたら、アキは絶対に理由を言わないの。とにかく黙っていてねの一点張りだったわ」
「それは俺の精だろ? そんなことを俺が知ったら、養子縁組のことが絶対になってきて、アキに有無を言わさないようになるのではと思ったんだろ?」
「今でも聞いていないけど、今までのアキの行動を見てたら、多分そんな気がします。アキは必死になって難しい試験に合格したのよ。普通だったら手を叩いて喜んであげなければいけないのに、複雑な気持ちでした。私も黙っているのがとても辛かったけど、別にお父さんを騙すつもりはさらさらないし、いつかは分っていただけると、そればかりを思ってきました」
「……」
「アキも、お父さんに同行してアメリカあたりに行っても、お父さんの手助けをしたくてもそれが出来ない、簡単に通訳出来るのにそれが出来ない。言いようのない辛さを味わったと思うの」
「……」
「幸いなことに、悟さんという最良の伴侶を得られたし、お父さんの心も変わってきたと思い、今度はリコの為に一肌脱ごうと考えて、いても立ってもおれなくなって、此処に出て来たのだと思うの。……アキそうよね?」
典子はアキの顔を見た。典子の顔は、辛い思いが解けてほっとした顔だった。アキも今まで隠してきたことが明らかになり、肩の重しが取れたような気がした。にっこりと笑って、父の誠一郎を見た。
「お父さん、お母さんの説明の通りなの。今まで黙っていてごめんなさい。怒りたかったら私を思い切り怒って。でもね、お父さんのお蔭で通訳士の資格が取れたと思ってるの。お父さんに反発したお蔭で、大きなお土産を貰うことが出来たと思ってるの。私には出来なかったけど、リコが立派にやり遂げてくれるから、お父さん機嫌直してくれる? アキもリコを絶対に応援するから。悟さんもいるし謙二さんもいるから、もう少ししたら、お父さんの思ってた通りの世界が開けてきそうな気がしてるの」
「……分った。……もう何も言うな。……悟、謙二すまないな。醜態を見せてしまって。こんな親父だが、宜しく頼むわ」
誠一郎は、小さく力なく語った。リコは自分の知らないところで、姉が辛い思いをしながら、しかも、そんな素振りを微塵も見せずに、明るくこの妹に接してきてくれたのだと思い、急に泣けてきた。悟が謙二に顎と目で合図した。
「エェー、飛んだハプニングと言いますか、嬉しいハプニングと言いますか、アキ姉さんの登場で、お父さんの腰が砕けるところが見れました。それでは気を取り直して最初からやり直しましょう。宜しいでしょうか? ……お父さん、いいですか?」
「……よっしゃ。こうなったら恥の上塗りだ。何処からでも来い」
誠一郎は開き直った。だが、もう顔は笑っていた。別な喜びが湧いてきたのである。
「アキ姉さんもリコさんもいいですね。……えェー、アキ姉さんが登場しましたから、アキ姉さんには、受付と社長秘書の二役をやっていただきます。アキ姉さんよろしいでしょうか?」
「はい。任せといて」
「心強いご返事ありがとうございます。リコさんは、この四人で、全て英語で迫真の演技をしますので、よーく見て参考にしてくださいね」
「分りました」
「じゃあ、まず、アメリカ人のご夫妻が、一階の受付にいらしたところからお願いします。……どうぞ」
両親が演じるアメリカ人夫妻の片言英語と、謙二とアキの流暢な英語が場内に響き渡った。場面を次々に変化させながら進行して行った。最後は、アメリカ人夫妻が別れの挨拶をし、ニコニコしながら部屋から出て行って終了した。
こうして養成講座は、予期しないとんでもないハプニングはあったが無事終了した。全員を何ともいえない安堵感が包んだ。
リコが就職する際に、与えられた業務をスムーズにこなせるようにという目的でスタートした、いわば、リコの為の養成講座であったが、思わぬ展開があったりして、目的以上の成果が得られたような気がした。計らずも、家族の絆を深くした講座であったとも言える。
悟は大変満足そうな顔をしてアキの方を振り向いた。アキは胸の辺りで小さく拍手して悟にウィンクした。良くやったわね。ご苦労様、そして、ありがとうと心の中で呟いた。
誠一郎は、終わると同時に悟に歩み寄り堅い握手をした。謙二とも握手した。感謝の気持ちが滲み出ていた。
会社の会議室での養成講座が終わると、みんな自宅のリビングルームに戻り、コーヒータイムとなったが、悟は考えることがあってアキに囁いた。
「あのさ、ちょっとお父さんに聞いておきたいことがあるんだけど、どっかで話出来ないかなあ」
アキは悟の脳にまた何かくっ付いて来たと思った。急ぎ足で父親のもとに行き小声で話した。そして、アキの手招きで、悟は二人の後をついて行った。社長室のデスクの横のソファに通された。悟は社長室には初めて来た。
「悟、聞きたいことがあるそうだが、何だ?」
「急にすみません。考えるところがありまして、お父さんのお考えをお聞きしておきたいと思いまして」
「どういうことだ?」
「こういうことを私が申し上げるのは、はなはだ筋違いだと思っております。気に障りましたら、どうかお許しください」
「分った」
「お伺いしておきたいのは、ただ一点のみです。お父さんのお考えの中に、業務拡張のことはおありでしょうか?」
アキは耳を疑った。悟は何を考えているのだろう。父の会社のことに口出しするなんて、考えられなかった。
「業務拡張? 会社のか?」
「はい。そうです」
「もっと具体的に話出来ないか?」
「思い切って申し上げます。弟と先ほど茶店でいろいろ話したのですが、お父さんの会社と弟の会社は、貿易という括りをすれば似ているが、営業品目は似て非なるものと言っておりました」
「その通りだな」
「そこで、考えたのです。お父さんの頭の中に、その似て非なるものを、似て似たるものにするようにしたいという考えがあって、将来の会社経営の計画の中に、業務拡張の一環として、それを取り入れるつもりがあるかどうかを、お聞きしておきたかったのです」
誠一郎は、悟の弟の話が出て以来、あることを考えていたが、それを目の前でずばりと言われ、飛び上がらんばかりにびっくりした。この男は、どうして俺が考えていることが分るのだと恐ろしくなった。完全に見透かされていると思った。暫らく口を開くことが出来なかった。
アキは、もはや悟の考えや行動が次元を超えたところにあると思った。遠い将来を見据えた考え方から来ていることは薄々は分るが、今、何故このことが出てくるのかが理解出来なかった。しかも、部外者が会社の経営のことに口を挟むなんて。
「それを聞いてどうするのだ?」
誠一郎は少し強い口調で言った。
「理由は聞かないでください。ただ計画があるかどうかだけ教えてください」
誠一郎は悟の顔を凝視した。悟の性格は充分に分ってきた。今や、最も信頼のおける人物である。アキの婿養子になってくれたらと思うことしきりだった。その悟の口から、自分が考えていることをずばりと言われて、激しく動揺した。
「話す前に、一つ聞いていいかな?」
「はい」
「悟は似て似たるものにした方がいいと思ってるのか?」
「いえ、いいかどうかを部外者の私が言うべきではないと思います。それは社長が決めることです」
「うん、そうだな。……ということは、今現在、俺がそういう考えをしているかどうかを聞きたいのだな?」
「はい。そうです。もしお答えいただけない場合は、それはそれで結構です。この話はなかったことにしてください」
誠一郎は、暫らく顔を天井に向けて目を閉じた。気になるのは、答え方によっては、悟や謙二が反発してくることだった。そうなると、元も子もなくなってしまいかねない。それが怖かった。だが、これまでの悟のとってきた行動は、ことごとく納得するものだった。教えられることが随分多かった。そのことを考えたら、確かに会社のことだから、直接悟には関係ないことかもしれないが、悟の考えに乗ることはやぶさかではない。いや、むしろ計画の実現には、この男がどうしても必要だと思っている。いずれは話さなければならないことなのだ。早いか遅いかの違いである。
「もし、そのつもりだと言ったらどうするのだ?」
「お言葉を返すようですが、つもりの話はお聞きしたくありません。はっきりとそうだとおっしゃってください」
悟の鬼気に迫る話しぶりに誠一郎はたじろいだ。さらに悟の目をじっと見据えて、とうとう、ほんとのことを言わざるを得ないと判断し、観念した。
「そうだ。計画の中にある」
「それは間違いございませんか?」
悟は強い口調で念を押した。
「間違いない。その計画を、来年度にかけて実施するつもりだ」
悟の厳しい顔つきが、急に明るくなり穏やかになった。それを見て誠一郎はさらに驚いた。そしてこの男が、何故か急に愛おしくなった。観念した顔が笑顔に変化した。
「悟、良かったら、お前が今考えていることを、包み隠さず教えてくれないかなあ」
「はい。謙二が産業スパイで捕まらないように努力します。今は、それだけしか申し上げられません」
誠一郎は、こんなことってあるのだろうかと思った。もう既に悟の頭の中には、完全な青写真が出来ている。そう思わざるを得ない。
「俺の計画実現に、悟も協力してくれる、と思っていてもいいということだな?」
「はい。微力ながらお手伝い出来ればと思っています」
誠一郎はこの時、会社の展望が大きく開けたと実感した。
「分った。悟ありがとう」
誠一郎は悟の手を強く握り頭を下げた。そしてこの時さらに、この男を近い将来、外部役員として迎え入れようと強く思った。
悟は、社長室を出て、アキを連れてそのまま五階の自分の部屋に行った。
「悟さん、お父さんから凄いことを引き出したわね。見ていて胸がスーッとしたわ。悟さんて素敵」
アキは悟に抱きついてきた。悟はアキの唇を愛撫した。長いキスの後身体を離して悟が言った。
「アキ、ごめん。これから少しやることがあるから、先にリビングルームに行っててくれないか?」
「分りました。何分ぐらいかかるの?」
「そうだな、二十分から三十分位かな」
「はい。じゃあ、待ってるわね」
アキがリビングルームに顔を出した時は、既に父親は、母親やリコや謙二たちとコーヒーを飲んでいた。父親の顔は何か安堵しているように見えた。終始ほほ笑んでいた。暫らくして両親が、ちょっと買い物があるからと言って部屋を出て行った。
コーヒーを飲み終わり、謙二は早速リビングに貼られた写真を一枚一枚じっくりと見て回った。喜びにあふれた写真を見て謙二は、花岡家に完全に溶け込んでいる兄の姿を見て感銘を受けた。こんなことは、思っていても、なかなか出来ることではないと思った。兄の素晴らしさを再認識させられたような気がした。
写真を見ている謙二の傍にリコが寄り添ってきて、写真の説明を始めた。時折り二人が大きな声で笑っているのが聞こえた。この姿を見て、アキにはお似合いのカップルに映った。むしろアキは、もしかしたら、もしかして欲しいと思った。これ以上の男性は、もはや見つかるまいと思った。幸いにリコも謙二に対して好感を持ってくれているようだし、謙二も満更じゃないような感じがする。
暫らくして、会社の五階から戻った悟が、アキの隣に腰を下ろした。両親はいなかった。
「あれっ、お父さん達は?」
「何か買い物があると言って、さっき出て行ったわよ」
「あ、そうなんだ」
「ねえ、悟さん、あの二人、どう思う?」
アキは、リコと謙二に聞こえないように小さな声で悟に言った。
「どう思うって?」
「まあ、鈍い人ね。良く見てよ、……ほら」
悟はアキに言われて二人を振り向いた
「おォー、いい感じだね」
「でしょう? どうかしら、正式にお付き合いさせたら」
「おいおい、弟は今仕事が面白くてたまらないと言ってるし、嫁は田舎からと決めているみたいだぜ」
「悟さんだって仕事が超忙しい時に、私にプロポーズしてくれたじゃない。仕事が面白いのは理由にならないわよ」
「あは、一本取られたな」
「それに田舎の女性っていうけど、ここも田舎よ、……でしょう?」
アキに言われて、電気が走った。
「なるほど。何も鹿児島の田舎じゃなくてもいいよな。うん。なるほどな」
悟はアキの顔をしげしげと見つめた。
「私の顔に何か付いてる?」
「付いてる、あんたは何て鈍い人なのって文字が付いてる」
「ふふ、失礼な顔ねこの顔」
アキは自分の顔をつねった。
「あはは、面白い。……だけど、謙二が田舎の女性に拘っているのは、別な意味があるような気がするんだよなあ」
「そうなの? 別な意味って?」
「田舎に帰って姉の手伝いをしたい。となると、やっぱり鹿児島の田舎の女性でないと、一緒に農作業できないと思ってると思うんだよな」
「あ、そうだわね、……でも、本気でそう思ってるのか疑問だわ。だって、今の仕事が面白くてたまらない訳でしょう?」
「問題はそこなんだよ。……だけど、俺には何となく分ってるんだ。謙二が実際にはどう思ってるのか」
「えっ、そうなの? どう思ってるの?」
「多分、謙二を夢中にさせてくれる女性と、謙二はまだ巡り合っていないと思うんだよな。だから、そういう言い方をして、自分を誤魔化しているんだと思う。ただそれだけだと思う。本音の部分では、今の仕事をずっと続けて行きたいと思ってると思う。絶対にそうだと思う」
「私もそう思うわ。きっとそうよ」
「だとしたら、アキが今思っていることが実現できらいいなと」
「ふふ、遠まわしに言わなくてもいいわよ、ほんとは謙二さんとリコを一緒にさせたいと思ってる。でも、今はそっとしてあげたい、と、こう言いたいのよね?」
「おや、どうして分るの?」
「もう、何でも分かるわよ。顔に書いてあるわよ。見て見ぬふりをしておきなさいって。……そうなんでしょ?」
「うん。ちょっとその件で、アキに相談したいと思ってたんだよ」
「何なの? 今はまずいことなの?」
「いや、ちょっとした作戦を考えているんだよ」
「ふふ、また始まった。今お話して」
「じゃあ、改めてアキに確認しておきたいことがあるんだよ」
「ええ、何なの?」
「リコと謙二が一緒になることに、アキが賛成かどうかだよ」
「まあ、私が反対するって思ってたの?」
「いや、そうじゃないけど、……じゃあ、……いいんだな?」
「当たり前よ。あんないい青年、何処を探してもいないわよ。リコには勿体ないくらいよ。……どうして? 何か気になることでもあるの?」
「いや、兄弟と姉妹が一緒になるって滅多にないことだから、……なんか、わざとらしくて、まずいかなと思ったもんだから」
「何よ、自分だって、心のバリアを持ってるじゃないの。そんなの取っ払いなさいよ」
アキは笑いながら悟にけしかけた。
「あちゃー、また一本やられた」
「ああ、いい気持ち、ふふ」
「よし、そうとなれば作戦開始だ。……いいか? 問題は謙二の方なんだよ」
「あら、どうして? 謙二さん、リコのことが気に入らないってこと?」
「そうじゃないよ、二人は今日会ったばかりだろう? もう少し時間を与える必要があると思うんだよ」
「だって、私は初日から悟さんに抱かれたわよ。ものすごく嬉しかったし、あれがあったから今日があるんでしょう?」
「俺たちは、レトロ列車で逢ってから、二ヶ月近くも時間があったんだよ? その後に逢ったから、初めてという感じがしなくて、ああなったんだろう?」
「そう言われればそうね。今思い出したわ。逢えるまでの悶々とした気分を」
「俺だって同じだよ、なにしろ、毎日逢いたい逢いたいと思ってたんだから、新宿で初めて逢ったときは、もう随分前から逢っているような気がしてたんだよ」
「実際に二人だけで逢ったのは、あの日が初めてでも、精神的には随分時間が経っていたって訳よね」
「だろう? だから、俺達と謙二たちとを同じに見ては駄目なんだよ」
「なるほど。納得。さすが私の悟さん」
「何だよ、上げたり下げたり、忙しいな」
「で、どういう作戦なの? 謙二さんがどうしたの?」
「見たところ、リコは謙二に対して好意を持っているみたいだけど、謙二はまだはっきりしたことが分らないから、どちらかというと謙二の方に作戦がいるんだよ」
「なるほど、そうかも。田舎の女性がどうのこうのということもあるから」
「そうなんだよ。しかも、こういうことは非常にデリケートな問題だから、慎重に事を運ばなければならないと思うんだよ。俺達やお父さんなんかが、ああだこうだと言うと必ず失敗する。だから、二人の気持が、自然とそうなるように持っていかなければならないと思うんだよ」
「賛成。そこで作戦ね」
「そうなんだ。俺が謙二を説得するのは容易なことだけど、謙二は謙二の考えがあるし、意外と頑固なところがあるから、乗ってくるかどうか分らないところもあるんだよ」
「そうね。それも考えられるわね」
「謙二とリコは似合いのカップルだと思うんだよ。絶対に一緒になって欲しいと思うんだよ。そう思うだろ?」
「ええ、思うわ。理想のカップルよね」
「うん、そこでアキに頼みがあるんだよ」
「えっ、私に? どんなこと?」
「お父さんを説得して欲しいんだよ」
「お父さんを? そこで何でお父さんが出て来るの? どういうことなの?」
悟は腕時計を見た。駅に行く時間が迫って来ていた。
「ああ、時間がないなあ、アキいいか、もし時間がなくなったら、この件は横浜に帰ってから電話で話そう。いいね」
「分ったわ、そうならないように、急いでお話しして」
「でだな、謙二は、お父さんから宿題を出されたみたいなんだよ。で、その宿題を二月末までに完成させて、郵送するそうなんだよ」
「ええ」
「それと、さっきの講座の時、謙二が習い始めた時の英会話の資料っていうか、教材をリコにあげてもいいと言ってたろ? これも郵送するとか言ってたろ?」
「ええ、そうだったわね」
「郵送させないで、宿題の打ち合わせのためだとか何とか言って、口実を作って神戸に行くように仕向けて欲しいんだよ。しかも二、三回くらいな」
「神戸で謙二さんに会うために、二月末までの期間に二、三回くらい、お父さんに出張して貰う訳ね?」
「英会話の教材も郵送させないで、神戸に出張した時に受け取って、その時、その教材のことで、二人の会話が弾むって考えはどうだろうか」
「ただ郵送して、はいどうぞとやるよりも、直接手ほどきを受けたら、より効果があるわね。なるほど、策士の考えることは違うわね」
「おい、コラ、これでも一生懸命考えているんだから茶化すな」
「ふふ、はい。悟さん、ステキ」
「あは、すぐ誤魔化すんだから、もう、……口実は何でもいいよ。肝心なのは、お父さんの出張に、リコも一緒に行かせることなんだ」
「……悟さん考えたわね。凄いアイディアね。そうすれば、回数を重ねるごとに、二人が親密になるのではという作戦?」
「そうなんだよ。親密作戦だな。ほらいつだったかな、お父さんの出張には、勉強の為に出来るだけリコも一緒に同行するように俺がお願いしたら、快い返事があったじゃないか」
「でした。でした。まさか、あの時からこのことを考えていた訳じゃないでしょう?」
「それはそうだよ、あの時は、純粋に主に海外出張をイメージして話したんだよ」
「そうよね。今回は急なお話ですものね」
「そうだよ。作戦として、今回その手を使うんだよ。それにはアキに、そういう方向になるように、お父さんを説得して欲しいんだよ。出来るかなあ」
「ふふ、おやすい御用よ。見てらっしゃい。完璧にやってみせるわ」
「失敗したら、さらに時間が掛かることになるぜ。……しっかりな」
「任せといて。十日おき位でいいわね神戸に行くのは」
「そうだな。そんな感じだな。あんまり回数が多くても逆効果だよ。弟の性格からして、変にとられたら元も子もないから、あくまで自然にな」
「はい。良く分りました」
「そして、さらに肝心なことがある」
「まだあるの?」
「お父さんに、この作戦をそれとなく話すんだよ」
「ええーっ、お父さんに話すの? まずくない?」
「だって、いずれはお父さんの承諾がいるだろ? 俺の考えでは、この話にお父さんは百パーセント乗ってくる筈だよ」
「凄い自信ね。確信してるみたい」
「まず間違いなく賛成してくれる。だから、アキから上手く持っていけば、必ず喜んでくれる筈だ」
「そうね。そうなれば、後のことが何もかもスムーズに行くわね」
「だろう? だから、お父さんには、神戸に行った時、なるべく謙二とリコが二人きりになるように、仕向けて欲しいんだよ」
「なーるほど。悟さんて、悪知恵が働くのね」
「そう、……悪知恵のサトル。おい、コラ、何を言わせるんだ」
「うふ、……じゃあ、早速作戦開始ね」
「うん。頼む、……今日の帰りの新幹線の中で、リコに対する印象を、弟にそれとなく聞いておこうと思ってるんだ」
「そうね、またお話聞かせてね」
「アイ、分った。時間内に終わったな、ふー良かった」
「それにしても、悟さんの頭冴え渡ってるわね。凄いわね」
「いや、そうでもないよ、ただこれと思ったら、頭が勝手に回り始めるんだよ。くっついたり離れたりしてな」
「ふーん、脳味噌の中、見てみたいわね」
「あは、腐ってたりして」
「まだ少し時間があるわね、あのね? 聞きたいことがあるの、……いい?」
「うん。何だろう」
「悟さんは最終的にどうしたいと考えてるの?」
「オォー、ある意味鋭い質問だな。俺の心をお見通しみたいだな」
「はい、そうです。どうも、このままでは終わりそうにないと思っています。ですから、良かったら私も、最後までの形を知っておきたいと思って」
「そう言うけど、アキのことだから、今までの経過を見たら、おおよそ想像ついてるんだろ? 違うか?」
「ええ、ま、だいたいは、こうなるかなあ程度は想像出来るけど、やっぱり、悟さんから完成青写真を聞きたいの」
「とうとう来たか、さすが俺が心底惚れただけのことはあるな。これで俺は、いつ死んでもいいや」
「フフ、殺しても死なない身体をしているくせに。……もう、変なこと言うんだから。……で、どんな形を考えているの? 教えて、……ねっ?」
「実は、これはアキに、近いうちにじっくり話そうかと思ってたところなんだよ。いい機会だから、今言おうかな。もちろん、これから俺が話すことは、あくまで俺の考えだから、最終的には、アキやお父さんお母さんに賛同してもらうことが、前提条件なんだけどな」
「ええ」
「まず、順番に話すから、反対だったら言ってな考え直すから、……いいね?」
「分ったわ」
「それと、考え方の基本には、花岡家に関わる全ての人が幸せになるように、という思いを込めて考えられていることを理解して欲しい」
「はい。とても嬉しいことだわ」
「実は、まとめてメモ書きしてあるんだよ。大事なことだから口で言うより正しく伝わると思ってな」
「あ、そうなんだ。いつ考えたの?」
「一週間ぐらい、前から思いつく度に書いてはきたものの、完全にはまとまっていなかったんだよな。だから、バッグに入れて、ずーっと温めていたけど、さっきお父さんとの話と、アキが通訳案内士の資格を持っているということが分ったから、それらを付け加えることで一応まとまった。今さっき五階の部屋で、項目を追加しながらメモとして完成させたんだよ」
悟は内ポケットからメモ用紙を取り出した。
「そうなんだ、凄いなあ、……うん、やっぱ凄い」
「何をブツブツ言ってるんだよ。……という訳で、はい、これがそうだよ。二部作ったから一部はアキが持っといてな。但し、俺が言うまで誰にも見せちゃダメだからな、いいな?」
「はい。そうします」
悟はメモ書をアキに渡した。メモ書には次のようなことが記されていた。
花岡家に関わる全ての人が、幸せになりますようにとの思いから、早川悟は次のようなことを勝手に考えてみました。
この実現には、お父さんお母さんはもちろん、亜希子の全面的な賛同がなければなりません。一つでも賛同できないことがあれば、お互いに意見を出し合って、考えを修正しなければならないと思っています。
下記のような手順で実行すれば、自然と成就出来るようになっています。
二〇一二年一月九日時点の記述です。
①花岡貿易商事株式会社のことについて
- 一月十日花岡貿易商事株式会社に花岡真理子が入社。(決定)
- 花岡真理子の今後のことについて
- 一般事務や経理、受付、国際電話、英語の書類作成、外国人の来客対応、海外出張等々、必要なすべての業務を一通り経験させる。
- 三年後の二〇一五年に社長秘書となる。
- 六年後の二〇一八年に常務取締役に就任。
- 九年後の二〇二一年に専務取締役に就任。
- 十年後の二〇二二年に代表取締役社長に就任。
現社長の花岡誠一郎は第一線から退き名誉会長に就任。 - 二〇一二年四月約款変更、取扱品目に画像診断機器、放射線治療機器、病院医療情報システム、人工透析機器等の販売を追加する。
- 早川謙二をヘッドハンティングする。
- 業務拡張に伴い社内体制の刷新を図る。
- 評価基準を年功序列から能力主義に切り替える。
- 二〇一二年十月関西支社を設立する。
②早川謙二の今後について
- 結婚を前提に花岡真理子と交際する。
- 出来るだけ早い時期に、現在勤務している会社を退職して花岡貿易商事株式会社に入社する。
- 入社後については社長一任。
- 頃合いを見て花岡真理子と結婚する。
③早川悟と花岡亜希子について
- 二〇一二年五月二十日結婚式と披露宴を篠ノ井で行う。(決定)
- 新婚旅行はしない。(決定)
鹿児島の母と姉夫婦に挨拶に行く。披露宴等は行わない。 - 渡米までの間、早川悟は単身赴任の形を取り、現在の社宅から出勤(会社の許可が必要)
花岡亜希子は篠ノ井の実家で暮らす。理由 → 家賃等の節約。 - 二〇一二年十月末渡米(約二年間の予定)
これを新婚旅行に置き換える。(決定) - 二〇一二年十月~十一月(未定)国際設計コンペの当選発表。
- 二〇一四年十月(未定)帰国。(早まる可能性あり)
- 帰国直前に東京都内に賃貸マンションを契約。帰国後入居。
- 二〇一五年十月~二〇一六年四月のしかるべき時期に環太平洋建設株式会社を退職する。
- 退職後都内に駐車場のある店舗付住宅を借りる。
- 住まいは3LDK~4LDK程度とする。
- 設計事務所とブティックが併設出来る規模の物件を探す。
- 開業。
④花岡亜希子と真理子に対する希望
- 花岡亜希子は、渡米までに建設業関連の専門
用語を完全マスターし、会話出来るようにしておくこと。
尚、通訳士の資格を持っていることによる利点は、次のようなことが考えられる。 - 利点1 米国滞在中の業務用の通訳がスムーズに出来る。
会社と交渉して通訳業務の委託契約をする。(会社が応ずるかどうかは未定)
一日当たりの報酬は四万円程度。従って一年間の報酬は、あくまでアバウトだが、二〇〇日×四万円=八百万円となる。もし二年間だと千六百万円程度になる。これは全て開業準備金としてストックしておく。 - 利点2 米国での休日の観光旅行などがより楽しくなる。
- 利点3 ブティックを開業した時外人客への売り込みが出来る。このことをアピールすることで、他店との差別化を図り売り上げ増につなげる。
- 利点4 子供に教えることでグローバルな感覚を持った子供に育てられる。
- 花岡亜希子は、ブティックの開業に関する情報
を最大限収集しておくこと。
その為に、例えば仕入先などの調査や、必要であれば、実際に開業するブティックの業態をどうするかなどの、参考になる情報を得るために、米国出張の機会を有効に活用出来るようにすること。 - 花岡真理子は、一年~二年以内に通訳案内士
試験に合格し、登録を完了しておくこと。
(参考)通訳案内士法の規定によると、報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をする業を営もうとする者は、通訳案内士試験に合格し都道府県知事の登録を受ける必要がある、とある。従って自社の取引先との通訳には必ずしも必要とは思わないが、実力をつける意味からも取得しておいた方が良いと考える。 - 花岡真理子は、三年以内に秘書技能検定試験
の一級に合格しておくこと - 花岡真理子は、三年以内に医療秘書技能検定
の一級に合格しておくこと - その他、必要に応じて、法律で定められてい
る資格試験等を受験、業務に支障がないようにしておくのはもちろん、よりレベルの高い業務遂行が出来るように励むこと
アキは、一行一行をじっくり丹念に目で追った。そして、メモを見ながら手が震えてきた。さっき悟に尋ねられて、だいたいはこうなるかなあ程度は想像出来る、と言ったことを恥じた。とんでもなく凄いことが書かれていた。
遠い将来を見据えて、実に細かいことが記述されていた。しかも、独立開業やブティックのことなど、随分前に話し合ったことが、さも当たり前のように書かれている。
今まで驚かされることばっかりで、慣れっこになったつもりだったが、何と何ともう言葉が見つからない。アキは改めて悟の恐ろしいぐらいの凄さを感じた。
「何をポカンとしてるんだ? アキが考えてまずいところがあったら言ってな。修正するから」
「……」
アキは悟の顔を凝視した。
「どうしたんだよ。俺の顔に何かくっ付いてるかい?」
「悟さん、怖い」
「えっ、俺の顔が怖い? 嘘だろう? なんで?」
「顔は世界で一番好きよ。……怖いのは顔じゃないの。脳みそ」
「脳みそ? あはは、見たようなことを言うね」
「もう見たようなものよ。凄いという表現が陳腐に思えてくるわ。やっぱり、怖いがぴったり」
「どうなの? ざっと見て、何か意見ない?」
「このメモ名はいいわねえ。、……でも、メモにどうして名前付けるの?」
「名前を付けておけば、何かの時に、ややこしい説明をしなくてもいいだろ?」
「例えば、幸せの青い鳥に書いてあるようにする。……とか? ……ねっ?」
「そうそう、そういうこと、簡単に意思が伝わるじゃん」
「なるほど、いいわね、……英会話が出来ることで、こんなにも利点があるなんて、考えも及ばなかった」
「一つ質問していいかなあ」
「ええ、何?」
「通訳案内士の資格があることを、何で俺に黙っていたのさ」
「あ~あ、やっぱり言われちゃった。ごめんなさい。……そのことだけど、打ち明けようかと悩んだの。でも、アメリカに行った時、悟さんをびっくりさせようと思って打ち明けるの止めたの」
「やっぱりな。そんなことだろうと思ったよ。それにしても、さっきの会話凄かったね。流暢な会話で傍で聞いていて驚いたよ」
「会話の内容が簡単だったからだわ。専門用語が入ってきたら、なかなか難しくなるわね」
「建設業関連の専門用語をマスター出来そうかなあ」
「まだ少し時間があるから、何とかなると思う。悟さんも教えてね」
「だな。ところで、その通訳案内士登録証って一度見てみたいもんだなあ」
「今持ってきましょうか?」
「いや、今日はいいや。今度でいいよ」
「はい。それにしても、ここに書いてある千六百万円って魅力ねえ。ほんとに会社が予算組んでくれるのかしら」
「それは分らない。どっちみち、外部の通訳士は頼まなければならないから、費用は掛かる訳だし、上手いこと交渉してみるしかないな。単価を下げられるか、最悪ボランティアになるかもしれない」
「そうね。でも、もし上手く行けば、開業資金の足しになるから、凄い魅力よね。会社が契約してくれたら助かるわね」
「だな、それは、ま、交渉するとして、……他に気になることは? ない?」
「気になること? ……①も、②も、④も、いいでしょう? ③の早川悟と花岡亜希子についてだわね問題は」
「結婚式の後、渡米までの間単身赴任ってことだろ?」
「そうなの。結婚してからは、毎日一緒に暮らせると思っていたから、ちょっとショックね。でも、考えて見たら、今のパターンと一緒だから少しの辛抱だし、止むを得ないかなと思ったの」
「実は、その点を反対されるんじゃないかと思ってたんだよ」
「マンションの場合、毎月の賃貸料とか敷金とか権利金とか礼金なんて取られるんでしょう? バカにならないものねぇ。たった五ヶ月ぐらいだけど、だから逆にもったいないのよねぇ」
「今みたいに、毎週土・日にここに来ればいい訳だし、そうすれば、お父さんやお母さんやリコも、きっと喜んでくれそうな気がするんだよな。マンション代に払う金のことを思えば、往復の交通費なんて安いもんだよ」
「そうだわね。今年は一番大事な年になりそうだし、離れて暮らすよりは、リコと謙二さんとの進み具合も良く分るから、却っていいかもね」
「そうなんだよ。謙二は今の会社を辞めることになるかもしれないし、関西支社の設立やらのこともあるからなあ。俺たちが傍にいたほうが何かといいような気がするんだよ」
「そうだわね。一石二鳥、ん? 一石三鳥かもね。……うん。そうしましょう。来年からは、悟さんと死ぬまで一緒に暮らせる訳だから、大事なこの一年だけは我慢しましょう。はい。決定です」
「それとさ、アキからまだ全然聞いてないんだけど」
「えっ、何を? お話ししなければならないこと、あったっけ?」
「実際にやるんだったら、いまの決定で、却って好都合になったと思うんだけど、例の社員教育のスケジュール」
「……えっ、えっ、私、悟さんに話してなかったっけ? ウァー、ごめんなさい。……あら、やだ、お父さんに雷貰うところだわ」
「じゃあ、決まってたの?」
「そうなの。私って駄目ねェー、ああ、これじゃマネージャー失格ね。……ああ、情けない」
「アキらしくないね。どうしたんだよ」
「悟さんの注射が強烈過ぎて、その度に、一つずつ何かが忘れ去られていくみたい」
「あははは、俺の精にしやがって、負け惜しみもいい加減にしろ」
「ふふふ、こんな女でもいいですか?」
「バカ、何言ってるんだよ。じゃあ、今度から弱い注射に変えるかな?」
「イヤーン、お願い、それはダメ。今後気をつけますから」
「あははは、参ったなあ、もう、……で、どうなってるの?」
「ちょっと待って。部屋に戻ってノートを持ってくるから」
「いや、今は時間がないからいいよ。だいたい隔週の土曜日だろ? 初回はいつになっているかなあ、それだけは気になるな」
「隔週の土曜日で決まったんだけど、確か初回は、一月二十一日の土曜日だったと思う。スケジュール表持ってこなくてもいい?」
「うん、いいよ。……で、マネージャーとしては、……」
「費用の事でしょう? それはもう、ばっちり予算取っちゃった」
「そうじゃないよ。それはアキに任せているんだから聞く必要ないよ」
「あら、そうなの? 気にならないの?」
「全然気にならないと言えば嘘になるけど、しっかり者のアキのことだから、俺が敢えて口をはさむ必要ないだろ?」
「じゃあ、何なの?」
「何時から何時間とか、正確な人数だとか、講座のテーマとか、いろいろあるだろう? 俺としては、資料をそろえる都合もあるし、その辺を聞いておきたいんだよ」
「そのこともばっちり決まっています。だから、部屋に帰って取りに行こうとしたんです」
「そうか、じゃあさ、いろいろ早めに準備しておかなきゃならないから、今夜でもメールしといてよ」
「あ、そうだわね。分りました」
「で、実際にはいつ頃決まってたの」
「ゴメンナサイ。年末です。イブが終わった次の週の月曜日」
アキは聞き取れないくらいの小さな声で言った。
「えっ、ほんとかよ、呆れた。それはひどいなあ。……ま、もっとも、年末は女性は忙しいからなあ。責めるの止めようか」
「フフ、やっぱり優しい。……大好き」
「そうか。そうなると、横浜で今迄通り一人で寮に暮らすとなると、単身赴任するってことになるから、一石四鳥になるな。……一石四鳥って、どっかで聞いたような気がするなあ」
「そうよ独立する時の話よ。仕事と家事と子供の世話、それと女としてのお勤めの話」
「ああ、思い出した。……あは、そうだったね」
「じゃあ、合せて二石八鳥? ……なの?」
「言葉が勝手に遊んでる感じだな」
「それにしても、よくまとまっているわね、このメモ」
「今の段階での、俺が思ったままのメモだから、時間が経てば考えも変わるかもしれないし、もっといい考えも浮かぶかもしれないから、ま、今日のところは預かっておいてくれる? そして何か意見があったら言ってくれる?」
「はい。良く分りました。全体像がはっきり見えてスカッとしました。後はこの通りに行くようにすることだわね」
「そういうことだな。……おっと、もうこんな時間だ。早めに出て、例の喫茶店に行こうよ」
「そうしましょう」
その時、リコが近づいて来て言った。
「お兄さんちょっとお願いがあるの。私の部屋に来て欲しいの」
「えっ、どうしたの? お姉さんも一緒じゃ駄目か?」
悟は、いくら何でも、妹の部屋に行くのは躊躇した。
「……うん。じゃあそうして、ついて来て」
リコは、壁の写真を見ている謙二の方に行って、二言三言喋って戻って来た。
二階のリコの部屋に三人で入った。悟は何だろうと首をひねった。リコは、白い封筒を机の引き出しから出して、悟の前に出した。
「お兄さん、これを帰りの新幹線の中で、謙二さんに渡してください」
アキは、いよいよリコの恋が始まったと直感した。
「手紙か?」
「そうなの。お礼の手紙と写真」
「今日は、謙二の体験談を聞いたりロールプレイングをしたからな。そのお礼だ。それはいいことだな。謙二は喜ぶぞ」
「じゃあ、お願いします」
「リコから直接渡したらいいじゃないか」
「ちょっと恥ずかしいから、お兄さんにお願いします」
「そうか、これを新幹線の中で渡せばいいんだな? 分った」
「それとこれ、ありがとうございました」
リコは、悟から預かっていた写真を返そうとした。
「ああ、あの時の写真な。欲しくないのか? 欲しかったらあげてもいいんだよ。もっとも、今日一杯撮ったからいらないかな」
「いただいてもいいの?」
「欲しいか?」
「……はい」
リコは、恥ずかしそうに赤い顔をした。悟はリコを可愛いと思った。
「じゃあ、あげるよ。俺はまだ一杯あるから」
「ほんと? 嬉しい。大事にします。……じゃあ、いただきます」
「田舎で撮った写真だから、一枚くらいあってもいいかもよ」
「お兄さん、ありがとう」
アキは、またリコが泣き出すのではと心配になってきた。
「それとリコ、……こんなこと聞くのデリカシーに欠けると思うけど、聞いていいかなあ」
デリカシーに欠けると思うんだったら、言わなきゃいいのにどうして言うの? 何を聞きたいの? アキは悟がまた変なことを言い出すのじゃないかと気が気でなかった。
「何でしょう。答えられることはちゃんと答えます」
「うーん。やっぱ止めとこうか、……俺はどうもいけないな。リコのことをもっと知っておきたいと思うと、ついつい、考えが勝手に言葉になってしまうから」
「お兄さん、途中で止めるの男らしくないですよ。私は大丈夫ですから言って見てください」
「俺がリコのお姉さんに対して、そうだったものだから、リコもそうなんじゃないかなあと思ってな? 聞いてみたかっただけだよ」
「お兄さんがお姉さんに対する気持ち? 最初に出会った時のことですか?」
「そう、そうなんだよ、あの時、はっきり運命を感じたんだけど、その時は分らずに、後になって、ああ、そうだったんだと思ったんだよ」
「え、え、何だろう。それを聞いてお兄さんはどうするの?」
アキは、悟が何を言いたいのか大体の察しがついてきた。今ここで言うべき? 聞いてどうするつもりなの?
「リコの望みが叶えられるように、一途一心で考えようかなあと思って」
「私の望み? お兄さん何なの? 何でも聞いてください。お兄さんだったら何でも言います。私、兄さんが大好きだから」
「そうか。ありがとう。リコが今思っていることを俺に伝えることで、俺はリコの為になるように行動するけど、それでいいかな」
「何の話か分らないのに、答えようがありません」
「それはそうだな。……じゃあ言うよ? リコは、俺の弟のことどう思ってるの?」
リコはある程度予測はしていたが、ズバリ言われて少し慌てた。アキは、あ~あ、とうとう言っちゃった。そっとしておこうと言ったのは、どこの誰だったっけ?
「どう思うって、……どう応えたらいいのかしら」
「弟のこと好きか?」
「……はい。好きになりました」
「一目惚れ?」
「……はい。そうです」
リコの顔が真っ赤に染まった。恥ずかしいそうな顔になった。
「そうか、そんなこと聞いて、気を悪くしたんじゃないか?」
「いえ、とっても嬉しいです。お兄さん、ありがとう」
「そうか、分った」
「この前、謙二さんの写真を見せてもらった時、気にはなっていたのですが、今日一日謙二さんの傍にいて、この人と一緒に人生を歩めたらいいなあ、と思うようになりました」
「うん」
「でも、今日初めて会ったばかりだし、少し不純かなあと思ったんですが、気持ちを抑えられなくて悩んでいました。近いうちに、お兄さんとお姉さんに相談しようと思っていました」
「そうか」
「そこに、お兄さんから今話が出て、打ち明ける気になりました」
「そうか。良く打ち明けてくれたね。ありがとう。……この話は、ここだけの話にしておくから心配ないよ。な、アキ」
アキは、リコの思いが、想像した通りだったことに安堵したが、デリケートなことだけに、慎重に話さなければと思い言葉を選んだ。
「ええ、で、こんな話するの野暮というものだけど、リコはどうして欲しいの? 悟さんに何かして欲しいことあるの?」
アキはリコに、姉としての優しい眼差しを向けながら言った。
「いえ、今は悟お兄さんから、謙二さんに手紙と写真を渡していただくだけでいいと思います。あれほどの方ですから、もしかしたら、恋人がいらっしゃるかもしれませんから、今はそっとしておいてください。お願いします」
リコからそっとしておいてくれと言う言葉が出た。相手の心に、土足で入りたくないという、謙虚でけなげな気持ちが伝わってきた。
「そうか。リコ分った。もう何も言うな。俺とアキ姉さんが、リコの思いをしっかり受け止めたから、リコは今まで通り振る舞えばいいよ。それでいいだろ?」
「はい。すみません、我が儘言って」
「……これだけは分って欲しんだ。リコを絶対に幸せにするんだということを、なっ?」
「お兄さんの私に対する気持ちは、随分前から感じていました。ほんとにありがたいと思っています。そのお兄さんの気持に応えられるように、一生懸命に頑張る覚悟です。これからもお願いします。私を支えてください」
「よっしゃ、分った。これからも何でも相談してな? そうしてくれた方が俺は嬉しいから」
「はい、そうします。……打ち明けて、気持ちがとっても軽くなりました。お兄さん、お姉さん、ありがとう」
アキは、悟は、リコの謙二に対する動かない気持を、本人の口から直接聞きたかったのだと思った。直接聞くことで、それを頭に入れながら、間違いのない結論に導こうとする、悟特有の考え方なのだと理解した。
「アキ、この件で何か言うことないか?」
「いえ、ありません。完璧です」
「あ、それからリコ、もしもだよ、謙二から、リコの携帯の番号を教えてくれと言われたら、教えてもいいかい?」
「……はい。構いません。むしろ嬉しいです。是非教えてください。私、謙二さんから電話来るの待っています」
「そうか、良く分った、じゃあ、そういう場面になるかどうか分らないが、その時はそうしよう」
「リコから質問いいですか?」
リコがニヤニヤしながら聞いてきた。
「お、何だリコ、ニヤニヤして」
「ということは、お兄さんもアキ姉さんに一目惚れだったのですね?」
「おっと、来たな? そういうこと。一目見て完全にいかれちゃった。だけど、その場で言う訳にいかないから、博多で別れてから、もう狂いそうになったよ」
「お姉さんはどうだったの?」
「あら、リコが一番知ってるくせに何よ。私に言わせるの?」
「うん。聞きたい。だって、想像はしていたけど、ちゃんと言葉で聞いていないもの」
「まあ、聞くだけ野暮というものよ。一目惚れもいいとこよ、寝ても覚めても、明けても暮れても、悟さんのことばっかり浮かんできて、他のことは何にも考えられなかったんだから」
「あ~あ、甘みたっぷりで美味しかった。ご馳走さまでした」
「まあ、リコったら、コラッ、人に言わせといて何よ」
「あはは、一本取られたな」
「憎たらしいんだから、もう」
アキは言いながら、たまらなく嬉しかった。
「じゃあ、時間だからそろそろ行こうか?」
悟と謙二を駅まで送りに行く途中に、昼食時に寄った茶店に再び入った。
「いやあ、今日はご苦労だったな。謙二は初めて来たのに、いろいろな場面に遭遇して疲れたんじゃないか?」
「とんでもない、凄く楽しかった。却って元気をもらった感じだよ」
「それにしても、宿題を出されたりロールプレイングしたり、どうなってんだろうね花岡家は」
「何言ってるのよ。みんな悟さんが仕掛けたことじゃない。他人事みたいに言って」
アキが中に割って入った。
「あはは、人聞きの悪いことを良く言うよ。だけど、言ってみれば、みんな花岡家のことを思ってやってることだからな」
「もちろん、それはとってもありがたいことだと思っています」
「謙二はどう思った? 今日の事」
「そうだな、一言で言って、羨ましかった」
「ほォー、どういう点が?」
「家族っていいもんだなあと、つくづく思ったよ。何か思い知らされたような気がする」
「どんなことを?」
「親子の愛情とか姉妹の愛情とか、思いやりとか温かみとか、普段触れたことのないことばっかりだったから、とても新鮮だったなあ、いやあほんといいもんだな家族って」
謙二のしみじみとした口調にアキが頷いた。
「これもみんな、悟さんが来るようになってからなのよ。それまでは、家族であっても家族でないような、そんな雰囲気だったのよ。だから、悟さんをみてて、人の力って凄いなあってつくづく思ってるの」
アキは感心したような顔で悟の顔を見た。
「それは違うよ。家族の一人一人がそれを望んでいても、何かの原因でその思いがせき止められていて、形になって実感できなかっただけだよ。ちょっとしたきっかけで、せき止められていた思いが、一気に流れ出して実を結んだということだろうな」
「お兄さん、質問があるんですが、いいですか?」
リコが手を上げた。
「お、リコの質問は最近鋭くなってきたからなあ、お手柔らかにな」
「ふふ、あら、私がこうなったのも、みんなお兄さんの精っていうか、お蔭っていうか、知らず知らずのうちに前の私じゃないことに気づいて、私自身が驚いてるのよ。この責任はどう取るつもりなのかしら?」
「おいおい、そもそも、今迄そういう言い方をしたことがあるか? ただスタイルが良くて綺麗で、明るくてお茶目なだけだったのに、最近はそれに、理知的って言葉がぴったりになってきたじゃないか。今まで隠れていたリコの計り知れない能力が、次第に表に出て来たということだろうな。これは凄いことだよ。な、アキ?」
「私もとても驚いているの。人間変われば変わるものだと、最近は、妹の余りの変わりように、前の妹のほうが良かったなあ、なんて思うことがあるくらいよ」
「お姉さん、じゃあ、今の私は気に入らないってこと?」
「ふふ、そうは言ってないわよ。とっても頼もしくなったって言ってるのっ。もう今は、完全に自立した女って感じがする、ね、悟さん」
「そうだな。いいことだよ。リコだからできたことだと思ってるよ。……それはいいけど、質問て何?」
「あら、危うくはぐらかされるところだった。……あのね、お兄さんて、次から次に新しいことを簡単にやってのけるでしょう? どうしてそんなことが出来るのか、今後の為に参考までにお聞きしたいの」
「それは簡単なことだよ。愛情と思いやりを、一途一心で考えることだよ」
「ふーん。もっと分り易く教えて」
「そうだな、例えばリコのことを例にとろうか?」
「はい。お願いします」
「お姉さんを交えて、リコといろいろな話を一杯してきたよな?」
「はい。そうでした」
「それを聞いて俺は、リコが何を望んでいるのか、どうしたいのかを理解出来たんだよな。だけど、理解するのは誰でも出来る。問題はその先だよ」
「……」
「リコの望みを実現するにはどうしたらいいかを、開けても暮れても考えるんだよ。トイレに入っても、シャワーを浴びてても、ご飯を食べている時も、とにかく、四六時中考えるんだよ。愛情と思いやりをもってそれこそ一途一心で考えるんだよ、そしたら、必ず良い案が浮かぶ」
「でも、考えても浮かばないでしょう? 普通は」
「そこなんだよ。一途一心の深さが違うっていうか、考える深度が違うんだと思う」
「集中力のこと?」
「うーん、少し違うんだよな。望みが叶えられたリコの姿を、徹底的にイメージするんだよ。そしたら、あら不思議。そのイメージが教えてくれるんだよ。こうしなさいってな」
「ヘェー、そうなんだ。訓練したらそうなるの?」
「そうだな、ある程度、何回も何回も訓練している間に、必ず出来るようになると思う。ロールプレイングだってそうだったろ?」
「そうなんだ。私もお兄さんみたいになりたいなあ」
「大丈夫だよ。リコはきっと出来るようになるよ。その素地はあり過ぎるぐらいあると思う。な、謙二どう思う?」
隣で聞いていた謙二が口を開いた。
「同感だな。ダイヤモンドに例えて、磨けば光るなんて良く言うけど、磨いても全然光らない人もいる訳だよな。素地の問題だよね。逆に素地はすごくいいものがあるのに、磨き方を知らないばっかりに、ガラクタで終わってしまって死んでいく人もごまんといると思う。その意味で、リコさんの場合は、持って生まれた素晴らしい素地だったのです。それを、せっせと磨いてくれた人が素晴らしかったものだから、一気に花が開こうとしている。ま、そんな感じだと思う」
「まあ、分り易い説明。謙二さん、お褒めいただいてありがとう。……ということは、お兄さんが現れなかったら、私もガラクタのままで死んでいく人間だった訳ですね」
「その可能性はありますね。朱に交われば赤くなると言いますが、どの人とお付き合いしたらいいかということが、如何に大切なことかを表していると思いますね」
「そうだとしたら、お兄さんを連れてきた、お姉さんに感謝しなければならないことになるわね」
リコが姉のアキの顔を見ていった。
「ふふ、今頃気がついたの? 遅いわよ。ね、悟さん?」
「あはは、威張ってやがんの。謙二の言うとおりだな。男同士でも女同士でも、男と女でも、いや会社と自分でもそうだし、もっと言えば、親子関係だってそうだと思うんだが、自分が成長出来るかどうかっていうのは、一つに相手との相関関係で決まるような気がするな」
「だな。素地のある人が一旦気づかされたら、後はその人の持って生まれた才能が勝手に動き出して、物事を成就しようと走り出す。私は今日来たばかりで浅いお付き合いですので、リコさんのことはまだ良く理解していませんが、リコさんはまさにそういう人だと思います。素晴らしい人だと思います」
謙二はリコの顔を見つめて言った。リコの顔が赤くなった。
「リコ、聞いたか? 滅多に人を誉めたことのないこの謙二が、リコに対して最高の賛辞を贈ったんだぞ。本気にしていいと思うぜ」
リコは益々赤くなった。
「謙二さんは座右の銘なんてあるんですか?」
その場を誤魔化そうと思い、リコが話題を変えた。
「座右の銘? ありますよ」
「良かったら教えていただけませんか?」
「ああ、いいですよ、私が座右の銘にしている言葉は、一意専心です」
「一意専心? どういう意味ですか?」
「決めた目的の達成の為、余計なことを考えないで、ただひたすら、そのことに心を集中させ努力すること、と言う意味です」
「あら、一途一心と似た意味ですね」
リコの言葉に、謙二は思わず兄の悟の方を振り向いた。そして、ニタッと笑った。
「そうですね。同じような意味ですね、私の場合、一意専心の延長線上に真の誠があると思っています。ですから、それを掴み取るまで努力しようと心に決めています」
「そうですか、素晴らしい考えですね」
「ありがとうございます。もう一つは……」
「えっ、二つもあるんですか?」
「あはは、根が欲張りなものですから」
「もう一つは何ですか?」
「敬天愛人です」
「どこかで聞いたような言葉ですね」
「そうですね。とても有名な言葉ですね。西郷隆盛が好んで使った言葉とされています」
「何だか奥が深そうですね」
「実に深いですね。私みたいな凡人には、この境地に到達するのは到底無理だと思っていますが、努力はしてみたいと思っています」
「どういう意味なのかしら?」
「いろいろなとらえ方があって、諸説あるようですが、人は天命というものを天から与えられ、それに従い生きているのである。天と同じように、誰へだてなく愛情を注ぎ、そして、自らを厳しく律し、無私無欲の人であることを心がけるべきである。そして、自分を愛する心をもって人を愛すること、つまり仁愛の人となることが肝要である、と私は勝手に解釈しています」
「すごい……」
「私じゃなくて、西郷さんが凄いのです」
「あのー、お願いがあるのですが」
「私にですか?」
謙二がリコの顔を見た。
「はい」
「何でしょうか」
リコは、バッグの中から小さなノートとボールペンを取りだした。そして、何も書いてないメモ欄を開いて謙二の前に置いた。
「すみません。これに今日の日付と、今の二つの言葉と、謙二さんの署名をお願い出来ますでしょうか?」
アキはいよいよ来たなと思った。リコの心が勝手に動き出したと判断した。
「いいですよ。でも、字が上手じゃないから、笑わないでくださいね」
と言いながら謙二は、ノートのページ一杯に日付と二つの文字を書き最後に自分の名前を書いた。凄い達筆だった。アキは、自分でも字には自信があったが驚いてしまった。
「まあ、凄くお上手な綺麗な字ですね。ありがとうございます。……嬉しい」
「恥ずかしいです。私は、例えば契約をいただいた時、もちろん直接会ったときはそうしますが、電話とかメールでお礼文を書く人が多いのですが、私はありがとうございました、と、心を込めて、お礼の手紙を書くことにしています。まだまだですが、その為には、出来るだけ読みやすく美しい文字になるよう努力しました」
「……」
「手紙はいつまでも残りますし、アナログなやり方ですが、自分の気持を素直に書けますし、その分、相手にもよく理解していただけるようですので、ずっと続けています」
アキもリコも、ただただ驚くばかりだった。一つ一つの行動の裏に、にじみ出る人間愛みたいなものを感じた。そして、アキは手紙という言葉が出て、自分が悟に対して果たしていない約束を思い出した。忘れた訳では決してない。同じ出すなら、より効果的なタイミングを見計らっているのである。
「でも、お忙しい中で、なかなか出来ることではないような気がしますが」
アキが口を挟んだ。
「いえ、それも仕事のうちですよ。実は私のやっていることは、この兄貴と会話してる間に生まれたことが大半なんですよ。……おい兄貴、黙ってないで何か言ってくれよ」
謙二は悟を引っ張り出そうと懸命だった。
「あはは、俺の出る幕じゃないよ。自分で尻拭いしろよ、と言いたいところだが、少し兄貴面しようかな」
「うんうん。頼む」
謙二が頷いた。
「謙二と俺は、姉はいるけど、アキとリコと同じように、この世でたった二人だけの男の兄弟です。田舎を出て、大都会のドロドロした空気の中で人並みの仕事をして行くには、そんじょそこらの努力では、とてもじゃないけど太刀打ちできない。だったら、兄弟二人が一つになって頑張ろうということになって、会うたびに、仕事の話で喧々諤々の議論を戦わしてきた」
「……」
「そうこうしている間に、二人に不思議な力が湧いてきた。その力が自信になり、さらに上を目指すようになり、今日があると思う。だから、謙二と俺は死ぬまで手を取り合って生きて行こうという、そんな気持ちが自然と育まれてきて、今や確固たる確信に変わったと言っていいと思う」
「……」
「謙二と俺とは、職種も違うし働く場所も違うけど、事あるごとに同じ考えを言うし、似たような行動に出ているような気がするんだよな。そういった意味だは一卵性双生児みたいなもんだな。……な、謙二?」
「そうだな。だから兄貴がくしゃみをしたら、下手すると俺は風邪をひいてしまう。とまあこういう関係だな」
謙二は悟の方を見て笑った。
「まあ、面白い表現ね。日本とアメリカみたいな関係ね。とても羨ましいわ。……とってもいい話だわ。……ね、リコ」
「もっと、ずっとずっとお話聞きたいわ」
リコは、謙二がノートに書いてくれた文字をジッと見ながら言った。
「そうして貰いたいところだが、もう時間が近づいてきた」
悟は腕時計を見ながら言った。
「えっ、もう? そうなんだ。なんだか淋しくなるわね」
リコが急に淋しそうな顔になった。
「リコは俺と同じように、謙二にも遊びに来て欲しいと思うかい?」
悟は、ニコニコしてリコの方を見て言った。アキはまた始まったと思った。
「はい。是非遊びに来てください。お願いします」
リコはけなげに頭を下げた。
「謙二、リコがああ言ってるけど、機会作れるかなあ」
「いやあ、なかなか難しいなあ、出来るとすれば、東京に出張した時ぐらいだろうなあ」
リコがさらに淋しそうな顔をした。
「やっぱり、神戸からじゃ遠いかな?」
「だよなあ、せっかくのお誘いだけど、ごめん。無理だと思う」
「東京には年にどのくらい出張があるんだよ」
「年というより、月に一回くらいはあるよ」
「いつも日帰りなんだろ?」
「そうだな。余程でない限り、泊まりってことにはならないなあ」
「そうか、やっぱりな。商談がタイミング良く土・日の前後なら、何とかなりそうだけど、ウィークデーじゃ何とも出来ないな」
「そうだな。まず無理だな。俺も、せっかく縁をいただいたから、出来れば遊びに来たいのは山々だが、残念ながら無理なような気がする」
さて、悟どうする。アキは悟の発想に期待した。
「お前の立場だったら、土・日の前後に商談を設定するのは訳ないんだろ?」
「いや、そういう訳にはいかないよ、相手はお客さんだから、相手のペースに合わせるのが普通だよ」
「今まではな? これからは、例えば五回のうち三回ぐらいはお前のペースに持ち込むっていうのは、何とか口実を作れば訳ないことだろう?」
アキはいよいよ来たと思った。巧みに相手をその気にさせる、天下一品の作戦に悟が出たと思った。どうなるのか楽しみになってきた。
「あはは、兄貴にはかなわないなあ、全部お見通しなんだから、もう返す言葉がないじゃないか」
「ということは? ということだな?」
「あはは、さっきのことを聞かされているしな、一途一心で深く考えれば良い案が浮かぶって」
「お前の場合だったら、一意専心だろ?」
「そうなるな。分った、分った。俺も出来るだけみんなに会いたいし、何とか考えて見るかな」
アキは悟の勝ちを心で宣言した。何というしたたかさだ。
「リコ聞いたか? 謙二の何とか考えるっていうのは、何とかするってことだし、何とかするってことは、実現するってことなんだよ。嬉しいだろ?」
「ええ、とっても嬉しいです。謙二さんお待ちしています」
「但し」
「えっ、条件付きか?」
「おそらく出来るとすれば、土・日しかない訳だから兄貴も一緒だろ?」
「そうだな。俺も土日しか時間取れない」
「だから、兄貴と一緒にここに来る。で、いいだろ?」
「俺が一緒でないとだめなのか? 子供みたいなことを言うなよ」
「それはそうだろう。よく考えてみろよ。俺は今日が初めてだぜ。一人で来れる訳ないだろう?」
「そうかなあ、アキどう思う?」
「私たちはちっとも構わないけど、謙二さんの気持は良く分るわ」
「さすがにお姉さんだ。物分かりがいい。それに比べたら、兄貴の奴、人の心がちっとも分っていないんだから」
謙二はアキの方を振り向いて小さく拍手した。アキは、これも悟の作戦のうちだと思っていた。
「やっぱり、そっかあ。俺も謙二の気持が分らなくはないんだけど、……分った。じゃあ、こうしよう、俺は今月の二十一日の土曜日から、隔週毎に此処に来ることになっているんだよ。だから、謙二もそれに合わせてスケジュール組んでみたらどうだ? 可能だろう?」
「そうか、隔週毎にここに来るようになっているんだ。そのうちの何回かを、出来るようにすればいいってことだな?」
「そういうこと」
「兄貴、その隔週っていうのは、ここに来て何かやるのか?」
「そうなんだよ。社員教育」
「えっ、社員教育? お父さんの会社のかい?」
「もちろんだよ、一年くらい続くかもな。……お、そう言えば、お前も手伝ってくれよ」
ああ、とうとうこうなってしまった。アキは呆れてしまった。
「おい、兄貴よしてくれよ。それだったら俺は来ない。勘弁してくれ」
「何を勘違いしてるんだよ。お前を教壇に立たせる訳ないだろう?」
「何言ってるんだよ。さっきもリコさんとロールプレイングを急にやらしたじゃないか、二度とその手は喰わないぞ」
「じゃあ、何か? お前はリコとのロールプレイングを、いやいややったのか?」
「いや、そうじゃないよ。言わせるなよ、もう、……すごく楽しかったよ。何回でもやりたいくらいだったよ」
人の心を吐き出させるのが実に上手い。感服の一語に尽きる。
「だろう? お前の貴重な過去の体験を、眠らさせておくには勿体ないだろう? 俺はそう思って、リコの為になればと思ってそうしたんじゃないか」
「うん。その気持ちは痛いほど分る」
「俺がお前に手伝ってくれと言ったのは、お前の過去の経験を俺も勉強して、社員教育の資料にしたいから、そういった意味で手伝ってくれと言ったんだよ。……それだったらいいだろう?」
「お、そういうことか。俺はまた、みんなの前に立って教育するのかと思ったよ。あは、早とちりした。うん。それだったら大いに協力するよ」
「そっか、さすが俺の弟だ、物分かりが早い。……じゃあ、決まりだな。アキ、リコ良かったな」
あ~あ、とうとう思い通りにしてしまった。
「ま、いつになるか分らないけど、来れる日が決まったら兄貴に連絡する。それでいいだろ?」
「いつになるかなんて言わないで、出来るだけ多く機会を作ってくれよ。頼むわ」
「よし、分った。お姉さんリコさん宜しくお願い致します」
謙二は改めて二人に向かって頭を下げた。
「あのー、謙二さん」
リコが真面目そうな顔で謙二を見た。
「はい?」
「私のことリコさんと呼ばないで、リコと呼んで欲しいのですが。その方が親しみが湧きますから」
謙二は戸惑った。いくら何でもという気持ちだった。
「はい。でも、やっぱりまだ」
「じゃあ、今日はいいですから、次にお見えになったらお願いします」
「はい。喜んでそうします」
いいぞ、いいぞ。リコもなかなかやるじゃないか。アキと悟は顔を見合わせた。
茶店を出て、悟と謙二は、姉妹に見送られて電車に乗った。謙二の手には、父親からの手土産の入った紙袋がぶら下がっていた。
悟は、ホームに立っているリコの様子がおかしいことに気づいた。今にも泣きそうな顔である。謙二との別れが余程辛かったと見える。
「兄貴、いろいろありがとう」
謙二が新幹線の中で口を開いた。
「いや、お礼を言うのはこっちの方だ。いろいろ無理も言ったりして、すまなかったな」
「いや、俺は兄貴の凄さを生で見て、改めて尊敬し直したよ」
「あはは、いつからお前は人をおだてるようになったんだ? 考えられないな」
「いや、ほんとだよ。凄いの一言だな。恐れ入りました。俺も見習わなきゃな」
「あはは、ま、その話はそれくらいにして、……で、どうだった。正直なところどういう印象だった?」
「姉さんは、兄貴が惚れただけのことはあるな。ほんとに素晴らしい女性だな。ああいう人はまず二人といないな。そんな感じがした」
「そうか、お前にそう言ってもらうと、何だか凄く嬉しいな。ありがとう。……リコのことはどう思う?」
「うん。純情無垢って感じで、実にいい女性だな。驚いたよ。俺の会社には、ああいう女性は見当たらないだけに、新鮮な驚きだったな」
「俺もそう思うんだよ。得がたい女性っていうか、そんじょそこらには居ないタイプだな。素晴らしい女性だよ」
「ほんと、そう思う。短い時間だったけど、そう思わせるだけの魅力のある女性だな。男性がほっとかないだろうなあ、ああいう女性は」
「お、いま思い出したけど、謙二には、俺たちの結婚式の日取りについてはまだ話してないよな」
「聞いてない。決まったのかい?」
「うん。決まった。五月二十日だ」
「えっ、ほんとかよ。意外と早くなったんだな。もう少し後かと思ってたけど」
「そうなんだよ。いろいろあって、逆算したらこの日になったんだよ」
「そっか、いよいよだな。良かったなあ」
「ありがとう。お前も出席してくれよな。予定にいれといてくれよ」
「五月二十日だな。分った。兄貴の結婚式に出席出来なければ生きてる意味がないよ。それこそ天罰が下るよ」
「あは、オーバーだな。おふくろも姉さんも多分出席は無理だから、せめてお前ぐらいは出て欲しいよな」
「うん。分った。で、どこでやるんだ? 東京だろ?」
「いや、式も披露宴も篠ノ井でやる」
「オォー、そうか。さすがに兄貴の決断は冴えてるね。いいねー、みんな喜んでくれたろう?」
「まあな。謙二も賛成してくれたようだな」
「常識にとらわれない兄貴らしいと感心したよ」
「ま、そういうことだから、とりあえず予定しておいてくれ。詳しくはまた連絡するから」
「分った」
「話変わるけど、お前は田舎の女性がいいと言ってたけど、やっぱり鹿児島の女性がいいのか?」
「そうだな、今の会社を辞めて、姉さんの農作業を手伝うとなると、自ずとそうなるだろう?」
「それはそうだな。それが一番だな」
「だけど、そうは思っても、これといった女性は、田舎ではなかなか居ないからなあ」
「謙二、ちょっと質問いいか? 聞きたいことがあるんだよ」
「うん、何だい? 急に改まって、気持ち悪いな」
「じゃあ、これから気持のよくなる話をするから、耳の穴大きく開いて聞けよ」
「気持ちの良くなる話? それは楽しみだな。何だい?」
「お前はほんとに田舎に帰りたいと思っているのか?」
「おいおい兄貴、どうしたんだよ急に真面目な顔をして」
「じゃあ、言い方を少し変えよう、今の仕事を放り出して、田舎に帰りたいのかと聞いているんだよ」
「……」
「今の仕事を放り出して、田舎の姉さん夫婦のしている農作業の手伝いを、ほんとにしたいと考えているのか?」
「そうズバリ言われると、何と答えていいか迷うなあ」
「ということは、まだ結論は出していない、と受け取っていいってことか?」
「ま、そうだな、……実はその件で、近いうちに兄貴に相談しようと思ってたんだよ」
「お、そうか。今じゃ駄目なのか?」
「兄貴と会う機会も余りないし、電話で相談出来ることでもないから、……うん、そうだな。今相談するかな」
悟は思っていた通りの謙二の返事に納得した。
「で? どういうことだ?」
「俺が今の仕事を好きだということはこの前話したよな?」
「聞いた。仕事が今面白くてたまらないって言ってた」
「そうなんだよ。死ぬまで続けたいくらいの気持なんだよな。そのくらい、俺にしてみたら天職そのものみたいに思えるんだよ」
「その天職を放り出して田舎に帰る? 謙二、そんなことしたら罰が当たるぞ」
「俺だってバカじゃないし、安易にそうは思っていないさ。……だけどなあ……」
「ははー、分った。お前はどうも察するところ、極めてくだらないことで悩んでるな?」
「えっ、兄貴それはないだろう? くだらないなんて」
「だってそうだろう? いいか? 良く聞けよ。今の仕事が天職だと言いながら、やれ姉さんの手伝いをするだの、田舎の女性がいいだの、お前の言ってることは支離滅裂じゃないか、……違うか?」
「そう言われれば、……そうだな」
「お前ほどの人間が、そういう支離滅裂なことを考えているなんて、俺にはどうも理解できない。原因は何なんだよ。お姉さんと農作業をしたいのか、それとも、気に入った女性が欲しいのか、どっちなんだ?」
「なるほど。問題点にフォーカスしたら、心の中が良く見えて来るなあ」
「バカ、何を感心しているんだよ。しっかりせんかい。切れ者で通ってるお前にしては、自分のこととなるとからっきしダメなんだなあ」
「そうだよなあ。どうしたらいいと思う?」
「あはは、これだからなあ。俺が図星なことを言ってやろうか?」
「うん、頼む。俺はもう、自分のことが分らなくなってきた」
「よっしゃ、引き受けた。……お前はこの前、都会の女性はどうも性に合わないと言ったよな?」
「うん。今でもそう思ってる」
「だけど、都会育ちの女性でも、お前のハートをくすぐる女性はいると思うけどなあ」
「それはそうだな。多分いる筈と思う」
「だったら、そういう女性がいたらいいってことだろ? 何も田舎の女性じゃなくてもさ。……それに、田舎の女性が、全てお前のハートに叶うなんてありえないだろう。何処の地域でも、これだと思う女性もおればそうじゃない女性もいる。……だろう?」
「それはそうだな。その通りだな」
「ちょっと聞くけど、お前の考えている田舎っていうのは、鹿児島のことだな?」
「うん。そうだよ。俺にとっての田舎は、生まれ育った鹿児島しか思い浮かばない」
「田舎にこだわるんなら篠ノ井も田舎だぞ。篠ノ井では駄目なのか?」
「篠ノ井? 神戸に比べたら確かに田舎だな」
「たまたま鹿児島の田舎に農作業をしている姉さんがいるから、田舎で嫁さんを貰って、姉さんの手伝いをするって発想だろ? 天職はどこへ消えたんだよ。……消えた天職? 笑い草にもならないよ」
「……兄貴、どうも俺の考えは、確かに支離滅裂だし焦点がボケてるな。兄貴に言われてみて、たった今良く分った。全くいい加減な発想をしているな俺は」
「いや、いい加減な発想とは思わないけど、問題は、謙二、お前の一生の問題なんだよ。……な、そうだろ?」
「全くその通りだな」
「だったら、もう少し焦点を絞って、なお且つ優先順位をつけて見ろよ。そうしたら答えが自ずと出てくるだろう」
「そうだな。俺は今バカだから、兄貴すまないけど俺に代わって優先順位をつけてくれよ。順番に整理してしっかり考えてみるから」
「おいおい、俺がお前の人生の優先順位をつけてどうするんだよ。自分で考えろよ」
「いや、俺は今、冷静になって自分を分析する自信を失った状態だよ、兄貴が今思っているままでいいから、言ってみてくれないか」
「あは、情けない奴だな。分った。じゃあ言うぞ。……よく考えて整理するとこうなるんじゃないか?
②伴侶は自分が気に入った女性ならいい。
都会と田舎は拘らない。
③伴侶が自分の仕事を理解し、
手伝ってくれるような女性だったら最高だ。
④あくまで黒田官兵衛を貫き通したい。
⑤今の会社には恩義はあるが、
場合によっては辞めてもいい。
「ざっとこんなもんだろ。……どうだ?」
「うーん。さすがに兄貴だな。いやはや驚いたなあ、ずばりこの通りだな。もう何にも言うことなし」
「ほんとにそう思っているのかよ。腹の中では違っていることを考えているんじゃないだろうな」
「おいおい、兄貴の前で、俺が嘘をついたことなど一度もないことぐらい知ってるだろう?」
「うん、だな。じゃあ、こういう優先順位でいいってことだな?」
「そうだな、なるほどこうしてみると、自分の思ってることがはっきりしてくるな。ほんとだこの通りだな」
「謙二、俺から提案があるんだが聞いてくれないか?」
「兄貴の言うことなら何でも聞くよ。どういう提案?」
「ずばり聞くけど、謙二は結婚のことをどう考えているんだ?」
「そうだな、将来のことを考えて、いい人がいたら、なるべく早く結婚した方がいいと思ってる。今の俺には、家庭を持つだけの収入は何とかなりそうだからな」
「そうか、分った。確認だけど、今付き合っている女性はいないんだな?」
「残念ながらいない」
「そうか。そこで提案だが、兄だからといって、謙二に強制するつもりは、これっぽちもないからな誤解しないようにな? 謙二の思うままを話してくれたらいいからな」
「了解。……で、提案って?」
「リコと結婚を前提に付き合う気はないか?」
謙二は悟の突然の提案にびっくりした。今日初めて会ってみて、かすかな思いはないことはなかったが、会ったばかりだし、まだそこまでは考えが及ばない。答えに窮してしまった。
「兄貴、突然どうしたんだい。リコとは今日会ったばかりだぜ。そう言われても答えられないよ。時間がなさすぎるよ」
「そういうけど、さっきお前はリコのことを、純情無垢って感じで実にいい女性だな。短い時間だったけど、そう思わせるだけの魅力のある女性だな。男性がほっとかないだろうなあ、ああいう女性は。と言ったじゃないか」
「確かに言った。凄く魅力的な女性には間違いないと思う。だけど……」
「そうか、ただそう思っただけのことか。俺は、お前にぴったりの女性じゃないかと思ったから提案したんだけど、思い違いだったようだな。しかし、あれだけの女性は、お前が足を棒にして探しても見つからないと思うけどなあ」
悟はわざと謙二に突っぱねるように言った。
「リコには好きな男性はいないのか? あれだけの女性だっら既にいるだろう?」
悟は謙二の出方を待っていた。謙二の心が揺れているのが、手に取るように分っていた。だが、さらに突っぱねた。
「彼氏がいようがいまいが、お前がその気がないんだったら、どうでもいいことだろ?」
「兄貴、そんな冷たい言い方しないでくれよ。彼氏がいるのかどうかを聞いてるんだから、答えてくれたっていいじゃないか」
「彼氏がいないと言ったら付き合うのか?」
「……うん。それだったら真剣に考えてもいいな。だけど、いくら俺がそう思っても、リコが俺のことをどう思ってるかだよな」
「今言ったことに誓って偽りはないな」
「……うん。兄貴に誓ってもいいよ。実はな? 二人でリビングルームの写真を見たりロールプレイングしたろ?」
「そうだったな」
「その時、リコの顔を見てふと思ったんだよ、この子と一緒に暮らせたらいいだろうなあとな。そしたら、そう思った途端に、得体のしれない何かが身体中を駆け巡るんだよ。俺にしたら生まれて初めて感じたことだけど、それから、リコを見るたびにそう思うようになったんだよ」
「じゃあ、リコに関して、お前の不安を俺が取り払ってやるから良く聞いとけよ。気持ちが段々良くなるからな」
「そうか。こういうことだったのか。やっと来たな」
「まず、リコには彼氏はいない。これは間違いない。信じてもいいことだ」
「お、そうか、ほんとか?」
「ほんとだ。信じろ」
「分った」
「それと、リコのお前に対する気持ちだが、知りたいか?」
「兄貴、知りたいかはないだろう? 一番気になるところだよ」
「そう言うけど、以心伝心って言葉があるぜ。何か感じなかったか?」
「そう言われれば、何となくいい感じではあったがな」
「だろう? そこで、リコから預かったものがあるから今渡すからな。中身は俺も分らないけど読んでみろ」
悟は内ポケットから、リコに謙二に渡してくれと頼まれた白い封筒を取り出した。そして謙二に渡した。謙二は少し驚いたような様子だったが、目の前で封を切った。中から数枚の写真と手紙が出て来た。謙二は、チラッと悟の顔を見て写真を見た。そして、おもむろに手紙を開いた。
「どういうことが書いてあるかは、俺に言う必要はないからな。後はお前自身で考えて行動しろ」
悟は謙二の顔をジッと見ていった。
「兄貴、ありがとう、……ありがとう。……やっぱり俺は、兄貴なしでは生きて行けないよ」
「何を言ってるんだよ、このバカ。言う相手が違うんじゃないのか?」
「……」
「ま、お前にはお前の考えがあるだろうし、それについて、いくらお前の兄だからといって、俺がどうのこうのとは言わない。お前の人生をどうするかは、お前が考えれば良いことだからな。ただ、俺はお前のことが好きだし、お前の将来のことを考えて提案したまでのことだから、後は自分でよーく考えて、責任のある行動をとればいいと思う」
「兄貴……、ほんとにありがとう。今宣言してもいいか?」
「いいけど、もっとじっくり考えてから宣言した方がいいんじゃないか?」
「いや、兄貴がどういう考えでこういう提案をしてくれたかは、もう言うまでもないことだよ。兄貴が提案したこと自体がもう既にれっきとした答えなんだよ」
「分った。で、何を宣言するんだ?」
「俺、早川謙二は自分の意志と責任で、花岡真理子と結婚を前提として交際します。そして彼女を世界一の幸せ者にします。ここに誓います」
「オォー、そうか良く決断してくれたなぁー。嬉しいなあ。……そうか。うん。良かった、良かった」
悟はこの上ない喜びの顔を謙二に向けた。そして、謙二と固い握手をした。謙二も破顔した。
「さっきの優先順位の①と③と④だが何か思うところはないか? まず①についてはこの通りだな?」
悟は話題を変えた。
「④については? あくまでもナンバー2でいきたいのか?」
「そうだなあ、俺には代表者よりも縁の下の力持ち、つまり参謀役が合っているような気がするんだよなあ」
「トップで采配を振るうよりも、トップを支える知恵袋の役をしたいということだな?」
「そういうことだよな」
「どうしてその役がいいと思うんだい? 謙二は、トップになるだけの素質は充分持ち合わせているような気がするがなあ」
「その方が自分に合ってると言うと理由にならないけど、その立場の方が居心地がいいというか、力を発揮できそうな気がしているんだよな」
「組織には、そういった役柄の人材は必要だと思うんだよな。ワンマン経営の泣き所はその辺にあるといってもいいからな。知恵袋とか参謀役が居なくて、独断専行して失敗するケースは山ほどあるからなあ。その意味では、ナンバー2の役割は計り知れないものがあるよな」
「俺もそう思うんだよ。トップはあくまで会社の顔として専念する。実務はナンバー2に任せる。それぞれの能力にも依るけど、両輪となって動けば、このコンビネーションって意外と凄い力を発揮することになると思ってるんだよ」
「なるほどな。で、黒田官兵衛に徹したい、と、こういう訳だ」
「そういうことだな。……うん。改めて考えると、やっぱり俺はその役の方がいいな。好きだな」
「⑤の今の会社には恩義はあるが、場合によっては辞めてもいい。……これは? 何か意見があるかな?」
「この場合によってはって、どういうケースがあるのか、いまいちピンとこないなあ」
「このケースはもうなくなったけど、田舎に帰って姉さんの手伝いをするんだったら、会社を辞めざるを得なかったんだろ?」
「そうだな。そういう場合はそうなるな。でも、それはもうなくなった訳だから、他に何が考えられるかなあ」
「その件で謙二に聞きたいことがあるんだけどなあ」
「何だい?」
「リコのお父さんの会社のこと、どう思う?」
「どう思うって?」
「そうだなあ、謙二は、今日初めてリコのお父さんの会社を見て回ったから、今日の今日じゃ考えを持ち合わせていないかもしれないけど、会社の将来性とか、今後どうしたらいいかとか何か意見ないかい?」
「二月末までに、関西支社設立についての報告書を提出することになっているけど、その中に、少し俺の思った改善策みたいなことは書くつもりだけど、 今のところはこれといって思いつかないなあ」
「リコと結婚するとなると、どうするんだ? 神戸で暮らすのか?」
「えっ、……あ、そうか。……今の会社にいる限りはそうなるよなあ」
「リコが反対したら? お父さんの会社を手伝って、と言われたらどうするつもりだい? リコとの結婚を諦めるのか?」
「……反対するかなあ」
「リコは明日から、会社の正社員として働くことはお前も知ってるよな」
「うん。聞いたから知ってる。……兄貴、教えて欲しいんだけど、リコに関して、将来的に社長としての何か考えっていうか、路線みたいなものがあるのかい?」
「どうしてそれを知りたくなったんだ?」
「今日一日の動き、特に兄貴の言動や、養成講座にロールプレイングを取り入れたり、普通は、いくら社長の娘だからって、あそこまではしないだろう? 俺には、あれは帝王学の初歩を教育してると映ったんだよな。だから、リコに関して、将来的に何か路線が敷かれているのではと思ったんだよ」
「さすがに謙二だな。鋭い観察力と思考力だな。お前の言う通りだよ」
「えっ、やっぱりそうか。道理で尋常じゃないと思ったよ。兄貴は何で俺とリコが付き合う話の前に、そういうことを言ってくれなかったんだよ」
「言ったら、付き合いをやめるのか? リコとの結婚を諦めるのか?」
「いや、そういう訳じゃないけど」
「だろう? 人生の中での大事さの優先順位は言うまでもないだろう? お前も、家族の大切さを言ってたじゃないか」
「うん、そうだ。兄貴の言うとおりだよ。それは認める。だけど……」
「よっしゃ、分った。じゃあさ、最後まで話を聞いてから結論を出そう。それによっては、さっきお前は、ああいう宣言はしたけど、リコとの結婚は、諦めざるを得ないということもあり得るとしようか? それならいいだろう?」
「……うん。まあな」
「じゃあ、話を進めよう。お前の推察通り、リコには完全に路線が敷かれていて、明日の入社はその第一歩となるんだ」
「うん」
「そして、十年後に今の社長は会長職に退いて、リコが代表取締役社長に就任するようになってるんだよ」
「ええーっ、ほんとかよ。十年後といってもリコは相当若いぜ、それでも社長に就任するのかい?」
「お前もいつも言ってるじゃないか、年齢で判断しては物事を誤ってしまうと。そうだろ?」
「それはそうだ。俺の持論でもある。なるほど、だから、今から十年計画で、社長にふさわしくなるような教育をしていこう、ということだな?」
「そういうことだ」
「なるほどなあ」
「それに、社長も十年後は七十歳になるからな、第一線で働くには無理じゃないが、早めに交代するメリットを考えた上でのことなんだよ」
「社長もよく決断したなあ」
「これには伏線があってな? 社長は今の会社を、ついこの間まで他人に譲ろうと考えていたんだよ」
「えっ、ほんとかよ、どうして?」
「社長は後継ぎと考えていた男の子に恵まれなかったから、養子縁組を考えていたんだよ」
「その話は養成講座の時お母さんが話してたな」
「ところが、アキに猛烈に反対されて諦めざるを得なかった。俺がアキと結婚するという話になって、完全に断念したんだよな、養子縁組のことを」
「なるほど」
「こうなったら、会社を今の重役の誰かに譲って、これからは、お母さんと老後を楽しむか、なんて言い出すようになったんだよ」
「そうか、お父さんとしては苦渋の決断という訳だ」
「そうだと思う。……そこで俺は、アキといろいろ語って、あることを思いついたんだ」
「それが、リコを社長にっていうことかい?」
「そうなんだよ。社長の頭の中には、女社長なんて全く考えも及ばない感じだったんだよ。そこで、俺が提案したって訳だよ」
「そうだったのか。社長、驚いたろう?」
「あの驚き様は今も目に浮かぶよ。青天の霹靂っていうか、目からうろこっていうか、腰を抜かしたよ」
「だろうな。目に浮かぶようだな」
「そこで、何故そういう提案をしたのか、俺がそう考えるに至った経緯を、家族全員の前で詳しく丁寧に説明したんだよ」
「会社の世代交代もスムーズに行くし、リコには目標が示されてやりがいが出るし、いいことばかりじゃないか」
「そうなんだよ。社長もやっと目が覚めたみたいで、それからというもの、社長の考えがガラッと変わってしまったんだよ」
「うん。分るような気がするなあ。肩にずしっとのしかかっていた重みが取れた感じがしたんだ」
「今までの悩みが吹っ飛んでしまって、嬉しかったんだろうな、まるで人間が変わってしまって、信じられないぐらいだったよ」
「ということは、今日俺が見た社長は、信じられない変化を遂げた後の社長だった訳だ」
「あはは、そういうことになるな」
「だけど、社長はいいとしても、肝心のリコが承知したのかい? 察するところ、リコは社長を嫌っていたんだろう?」
「そこなんだよ。今結論だけ話したけど、そうなるまではいろいろ伏線があるんだよ」
「オー、そうか。どんなこと?」
「その話はリコからじっくり聞けよ」
「お、そうだな分った」
「そういう訳で、結果的にリコも喜んでくれて、リコの夢実現に第一歩をしるしたってことだ」
「ほぉー、いい話だなあ。兄貴らしくって何だかスカッとするね。……うんうん、大したものだ」
「何を感心しているんだ。話はこれからだ」
「あ、そうか、どこまで話していたんだっけ?」
「会社の路線の話だよ」
「あ、そうだったな、で、続きは?」
「その路線の延長線上に、優先順位の⑤のことが問題になってくるんだよ」
「優先順位⑤の、場合によってはの場合のことか?」
「そうだ。そこにお前が絡んでくるんだよ」
「えっ、何で俺が絡むんだよ」
「お前の勤めている今の会社と、リコのお父さんの会社とは、貿易という括りでは似ている会社だけど、営業品目は似て非なるもの、とお前は言ったよな」
「うん。言った。社長の説明を受けながら一緒に回った時もそう思っていた」
「ところが、会社は来年度から、似て非なるものから似て似たるものに業務拡張を計画しているんだよ」
「えっ、ほんとかよ。それも兄貴の提案かい?」
「いや、それは違う。社長の考えだ」
「ヘェー、俺の会社と競合することになるのか。そこで、関西支社の話が絡んでくるってことか、なるほど、読めてきたぞう」
「いや、関西支社は何年も前からの計画らしいから、必ずしもそうとは言えないと思う。この業務拡張をする狙いは別なところにあるんだよ」
「あ、そういうことか。何だよその別な狙いっていうのは」
「優先順位⑤の場合によっては、だよ」
「場合によっては辞めてもいい? えっ、えっ、……もしかしたら」
「やっと気がついたようだな、そのもしかしたらだよ」
「……おいおい、兄貴、本気かよ。……えっ、俺が今の会社を辞めて、リコのお父さんの会社に入る?」
「もう説明はいらないようだな。そういうことだ。社長はお前にぞっこんなんだよ。定款を変えて業務拡張を計画して、その部署で思い切り仕事して欲しいみたいだぜ。嬉しい話じゃないか」
「……ちょっと待ってくれよ。……イメージが飛んじゃったんだよ」
「そうなれば、お前とリコは、お前たちの子供が跡を継ぐまで、ずーっと同じ会社で伸び伸びと仕事が出来て、万々歳じゃないか、……だろう?」
「兄貴、ちょっと質問していいか?」
「うんいいよ、何だ?」
「兄貴はいつ頃からこんなことを考えていたんだ?」
「お前が田舎に帰って、姉さんの手伝いを云々と言い出した時からだ。俺は率直にいって、その話を聞いてこれはまずいと思った。お前ほどの優秀な奴が農作業? いや、農作業を悪く言うつもりはもちろんないよ。……ないがだな、余りにも勿体ないと正直そう思ったんだよ」
「なるほど」
「そこで考えた。俺の好きな弟の為に、何かいい案はないものだろうかとな。出来ればお前と、身近なところで一生を暮していけたらいいな、と、そんなことも思って、それこそ、一途一心で考え続けた。その解決策が今まで話してきたことだ。……だけど、これは俺の考えであって、必ずしもお前が賛同するとは思っていない。お前の人生だから、最後はお前が結論を出すべきだと思ってる。だから、とても大事なことだから、良く考えて結論出した方がいいと思う」
「参考のために聞いておきたいのだが、もし俺がその方向で決断したとして、俺はどうすればいいんだ?」
「何もすることはないよ。多分近いうちに、社長が、お前をヘッドハンティングする行動に出ると思う。だから、今結論を出さずに、時期はいつになるかは分らないが、社長が行動を起こして、お前に連絡があるまでの間考えておけばいいことだよ」
「明日ってことも、あり得る訳だな?」
「それは、俺には分らないが、あり得ない話ではないな。正式には三月の役員会で承認されて、四月からの事業計画ということだろうけどな」
「そっかー。……なるほどなあ。……よっしゃ、分った。良く考えて見る。……だが、結果として、そのようにならなくても、兄貴、……いいんだろ?」
「もちろんだよ。後はお前が自分のこれからの人生と照らし合わせてみて、しかるべき結論を出せばいいことだよ。肝心なのは、謙二がその気になって結論を出さない限り、物事は一切進んで行かないということだ」
「だな。俺は人生最大の岐路に立たされた訳だ。結論の出し方によっては、リコとのことは諦めざるを得ないということだな」
「得がたい女性だから、実に勿体ない話だけど、そういうことになるな」
「分った。これで全てのことが俺の頭にインプットされた。今の会社のこともあるし、しっかり考えて結論を出そう」
「そうしてくれ。あくまでも自分で考えるんだぞ。兄貴の顔を立てたいからなんて、そんなくだらないことを考えるなよ、いいな?」
「うん、分った。兄貴、ありがとう」
「それと、リコの携帯の番号は必要ないか? 教えてもいいぞ」
「いや、今はいいや。これは、俺が今の会社を辞めることとセットだから、気持ちの整理がついて、その気になったら、兄貴に電話するから、その時に教えてくれ」
「分った。謙二が、リコの電話番号を教えてくれと俺に電話してきた時点で、優先順位⑤の、場合によってはを実行しても良いということだな?」
「うん。そういうことだな」
「念のため、重ねて言うけど、俺が謙二にリコの電話番号を教えるイコール、今まで俺が話してきた線で進んでも良いと謙二が決断した、と判断してもいいってことだな?」
「そういうことだな。……いずれにしても、良く考えて見る」
「よっしゃ、分った」