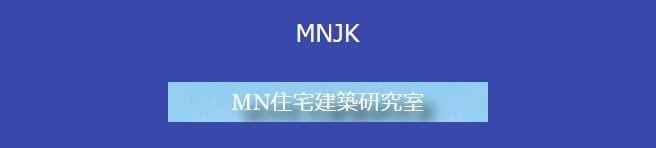地鎮祭の時に、神殿を囲うようにして、5本の竹の柱をたてます。そして、その竹を取り巻くようにしてしめ縄を飾ります。
そのしめ縄のつくりが、左縄(ひだりなわ)になっていることをご存知ですか?
左縄は普通の縄の綯い方(縄の方向が左下から右上)とは違って、左前に綯(な)う(縄の方向が右下から左上)ので左縄と言い、神社や鳥居の正門に下げられる、しめ縄と同じ意味を持っているとか、相撲の化粧まわしなど、神事の時の特有の綯(な)い方である。
ま、私は、この程度の表面的なことしか分かっていないのでありますが、世の中詳しい方もいらっしゃるものですね。「検索」などで調べますと、
古来日本では神社の注連縄と棺桶を縛る縄はともに『左縄』であった。『左』は吉と凶、浄と穢、正と邪の《両義性》を持っていた。左の両義性を括るのは『聖』であり、右に象徴される『俗』と対置される。
とか、
天の岩戸に隠れた天照大神(あまてらすおおみかみ)を岩を引きあけて連れだし、大神のまわりに『しりくめ縄』を引きめぐらした、という神話がしめ縄のはじめだといわれてます。
神前や神事を行う場所に張るときは、清浄な区域であることを示し、新年に戸口にはる時は、わざわいをもたらす神や不浄なものが内に入らないようにとの意味が込められています。
しめ縄は『しりくめ縄』の略したものといわれ『注連(じめ)』または『標縄(しめ)』とも書き『しめ飾り』ともいいます。
とか、
天の岩戸に隠れた天照大神(あまてらすおおみかみ)を岩を引きあけて連れだし、大神のまわりに『しりくめ縄』を引きめぐらした、という神話がしめ縄のはじめだといわれてます。
神前や神事を行う場所に張るときは、清浄な区域であることを示し、新年に戸口にはる時は、わざわいをもたらす神や不浄なものが内に入らないようにとの意味が込められています。
しめ縄は『しりくめ縄』の略したものといわれ『注連(じめ)』または『標縄(しめ)』とも書き『しめ飾り』ともいいます。
とか。
以上、頭が左巻きになってしまった私でした。